特異な天球三角形 ― 2009/08/11 09:55
今回の東海地震直前の宏観現象としては、FAXの送信エラーがあった。同報通信で幾つかのところにホームオフィスから送信したのだが、回線にノイズが入り、エラーが続出。何度も送り直す羽目になった。「きっと大雨で回線状態が悪いのだろう。」と思っていたが、地震による岩盤電流の影響であった訳。
その他、体調もおかしかった。毎回、地震等の前には、心臓の辺りが痛くなるのだが、今回は、特にひどく医者に行こうか思った次第。ところが、地震が起きてしまったら、全然、なんともない。
天球をみると、特異な天球三角形をしている。太陽を中心に地球→木星のベクトルと金星、火星のベクトルが直角交差している。直角の効果はどうかしらないが、以前、指摘した通り、木星と太陽の巨大な重力に挟まれる位置関係、日食にみられる様な地球と月の起動面の傾斜角が小さい状態。よく見ると、月の位置も金星→火星のベクトルと並行となっているのも不気味。
その他、体調もおかしかった。毎回、地震等の前には、心臓の辺りが痛くなるのだが、今回は、特にひどく医者に行こうか思った次第。ところが、地震が起きてしまったら、全然、なんともない。
天球をみると、特異な天球三角形をしている。太陽を中心に地球→木星のベクトルと金星、火星のベクトルが直角交差している。直角の効果はどうかしらないが、以前、指摘した通り、木星と太陽の巨大な重力に挟まれる位置関係、日食にみられる様な地球と月の起動面の傾斜角が小さい状態。よく見ると、月の位置も金星→火星のベクトルと並行となっているのも不気味。
片翼の蝶々(愚かな幻想の成れの果て) ― 2009/08/11 22:04
今日、帰宅したら会社から封書が届いていた。
夏季賞与の振り込み通知だった。金額をみて愕然とした。1ヶ月以上も遅れた上に、昨年よりも更に5万円以上も減額で、手取り額では、毎月の給与の半額に近い。
せめて引っ越し代位は出ると思っていたが、それも出ないので、家の購入はおろか、賃貸への住み替えも不可能だ。それにしてもこんな半端な額面であれば、貯金するにしてもどうしようもない。
これまで10年間にいただいた賞与を全額貯金して、ようやく住宅購入の当座必要な資金が貯まったが、もう、2度とこんなことはない。
佛大通信の授業料にも満たない。ここまで収入が減少したので、佛大にももう行けないだろう。
前にワンルームマンションで生活していたが、パチンコや悪所通いで生活費を全部使い果たしてしまっても、総合口座なので、マイナスでもやって行けた。
大体数十万円位、残高がマイナスになっていたが、夏季や冬季賞与で全部穴埋めして暮らしていた。それでもカードローン等は利子を返すのが精一杯だった。
今の賞与では、そんなことも出来ない。あっとう間に生活破綻だろう。
当然、サマージャンボも外れていた。
結局、私は永遠パラサイターでいるしかないのだ。
愚かな真夏の幻想の成れの果てである。
最近、ボヤーと庭を眺めていたら、揚羽蝶が2種類というか2個体やってくる。1匹は、元気にヒラヒラと飛び回って密を吸う。もう1匹は、フワフワと飛ぶが、こちらは、飛行速度が遅い。よくみると花の影で眠っている時に蜥蜴にかじられたのか、片方の羽の半分がダメージを受けており、人間が作った飛行機だったら墜落だが、この蝶は、それでもけなげにバランスをとりながら飛行を続けている。
カエルをみた小野道風ではないが蝶をみて、少しは、励まされただろうか。
まさか、自分は、間違ってもそんな健全な人間ではない。
夏季賞与の振り込み通知だった。金額をみて愕然とした。1ヶ月以上も遅れた上に、昨年よりも更に5万円以上も減額で、手取り額では、毎月の給与の半額に近い。
せめて引っ越し代位は出ると思っていたが、それも出ないので、家の購入はおろか、賃貸への住み替えも不可能だ。それにしてもこんな半端な額面であれば、貯金するにしてもどうしようもない。
これまで10年間にいただいた賞与を全額貯金して、ようやく住宅購入の当座必要な資金が貯まったが、もう、2度とこんなことはない。
佛大通信の授業料にも満たない。ここまで収入が減少したので、佛大にももう行けないだろう。
前にワンルームマンションで生活していたが、パチンコや悪所通いで生活費を全部使い果たしてしまっても、総合口座なので、マイナスでもやって行けた。
大体数十万円位、残高がマイナスになっていたが、夏季や冬季賞与で全部穴埋めして暮らしていた。それでもカードローン等は利子を返すのが精一杯だった。
今の賞与では、そんなことも出来ない。あっとう間に生活破綻だろう。
当然、サマージャンボも外れていた。
結局、私は永遠パラサイターでいるしかないのだ。
愚かな真夏の幻想の成れの果てである。
最近、ボヤーと庭を眺めていたら、揚羽蝶が2種類というか2個体やってくる。1匹は、元気にヒラヒラと飛び回って密を吸う。もう1匹は、フワフワと飛ぶが、こちらは、飛行速度が遅い。よくみると花の影で眠っている時に蜥蜴にかじられたのか、片方の羽の半分がダメージを受けており、人間が作った飛行機だったら墜落だが、この蝶は、それでもけなげにバランスをとりながら飛行を続けている。
カエルをみた小野道風ではないが蝶をみて、少しは、励まされただろうか。
まさか、自分は、間違ってもそんな健全な人間ではない。
徳島に移動中 ― 2009/08/12 09:33
日本列島縦断歩行は、香川に到着で、徳島に移動中。中国地区よりも、ペースが上がってきた。
体重は、喫煙を始めてから減少傾向が続いているが、筋肉が落ちて脂肪率が上がってきた。このままだと、再び体重が増加に転じるので、筋力をつける必要がある。但し、あまり、やり過ぎると痛風がぶり返すので、要注意。
5月頃には、どこまで増えるのかと思っていたが、六月を契機に減少を始めた。
痛風は、時々怪しくなることがあるが、今は安定している。下血もやはり、ジオン注射の効果からなくなった。最後の出血が先週の土曜日にあったが、その後は、何事もなく、順調。やはり、出血の原因は内痔核であったのかもしれない。
来週の土曜日には内視鏡検査であり、何もないことを願っている。
体重は、喫煙を始めてから減少傾向が続いているが、筋肉が落ちて脂肪率が上がってきた。このままだと、再び体重が増加に転じるので、筋力をつける必要がある。但し、あまり、やり過ぎると痛風がぶり返すので、要注意。
5月頃には、どこまで増えるのかと思っていたが、六月を契機に減少を始めた。
痛風は、時々怪しくなることがあるが、今は安定している。下血もやはり、ジオン注射の効果からなくなった。最後の出血が先週の土曜日にあったが、その後は、何事もなく、順調。やはり、出血の原因は内痔核であったのかもしれない。
来週の土曜日には内視鏡検査であり、何もないことを願っている。
歩道の整備が遅れている県として、奈良県が挙げられるが、兵庫県も次いで酷い ― 2009/08/12 23:37
今日は、どうゆう訳か、仕事がある日よりも早く目が醒めた。
仕事はなくても、海外の市場や為替等のデータのコンピュータへの入力は続けなくてはならない。平均値や偏差等のデータが狂ってくる為。
昨日、オーディオシステムのスピーカーをJBLのモニターに入れ替えた。その仕事で腰がずっと痛んでいた。
音を聴いてがっかり、全く、クラシック向きではない。特に最新の古楽器の音色が駄目。古いアメリカのシカゴシンフォニーとかボストンシンフォニー等の演奏は、面白く再生される。
ジャズをかけると俄然、冴えてくる。特にシンバルの音なんか凄い。ペットのミュートやトロンボーンのワウワウなんかも面白い。ベースの音は物足りない。
午後からは、先日、不動産屋にクルマで連れていってもらった物件について駅から実際に歩いてみることにする。鈴蘭台についたら、もう4時30分。空気がヒンヤリとしている。その後、梅田に出てきたが、気温差5~6℃位あるのでは。
実際にあるいてみて、今の自宅の場所よりも坂は少ないが、それでも傾斜はあり、大体25分位かかった。(途中写真等撮影しながらなので、余計に時間がかかる。)付近には、神戸親和女子大や中学校、小学校、幼稚園、兵庫商業高校等、幼児教育から最高学府まで全て学校が揃っている。今日、見に行った家も校庭の裏側であることは話した通り。
今日は、お盆休みの人が多く、僕が、家を撮影していると、むかいがわの方が犬(大きな奴)の散歩に行く途中なので目があってしまった。ドキドキしながら頭を下げた。
その時悟った。「僕は引きこもり症なのにご近所つき合いやっていけるだろうか。」
ここの地域は、自然には、恵まれすぎる程、恵まれているので、居住者の表情も明るく、人間的な余裕がある感じ。家並みもそうだが、今までの家に比べて1~2クラス上の階層の人達が住んでいるようだ。
僕が買う予定(かな)の家は、襤褸家でおとぎ話に「古家の漏りほど恐い物はない。」いうが、その恐ろしさが現実化している家。
暫く撮影しながら駅に引き返したが、狭い山道なのにクルマを滅茶苦茶飛ばすので、歩行者は危ない。小さな子供を道路脇を歩かせるのは恐い感じ。
歩道の整備が遅れている県として、奈良県が挙げられるが、兵庫県もついで酷い。京都とか滋賀とかの住民の人がみたら、よくこのまま放置しているなぁという感じ。
公園も子供の飛び出し防止の為に2重の囲いになっている。最近、クルマに乗っていないから判らないが、隘路の通過とか行き違い等で徐行しなければならないということやはみだし禁止の2重線を無視する様なことが当然の様に行われているのに平気なんだろうか。
はみ出し禁止については、最近の馬鹿でかいクルマではみ出さずに走行することは、不可能なので、こんなクルマを製造販売している自動車メーカーにも責任がありそうだ。
クルマは、鈴鹿サーキットやF1だけで十分だ。
徒歩で25分かかるので、自転車の利用も考えたが、危険なのでやはり、自動車かもしくは徒歩ということになるようだ。今回みた家にも車庫があるが、クルマで駅までいく人が多いようだ。駐車場は、結構、ある方なので困らないということなのだろうか。
往復50分間歩いて足が棒になった。1日約7000歩が稼げるので、日本列島縦断の達成時期が早まるか。
それよりも呆れたのは、電車の乗車時間で、鈴蘭台から阪急梅田まで特急で約1時間。つまり大阪までは、1時間30分もかかってしまうことになる。神戸までは、1時間以内で行ける。
住環境をとるか、それとも便利さをとるかということだが、何よりも、私に採っては、予算の問題がある。
ボーナス減額、会社の昨年度末決算をみても売上高が5%程度減少しているので、このままでは、ローンの査定も通らず、貯金も結局、なんやかやで浪費してしまって、そうなると家を買うチャンス等二度とないだろう。
家賃やマンション維持費、管理費、修繕費を支払うだけの経済的余裕の無い老後の暮らしを守る為に、一戸建てを買わないと、どうにもならない。
また、なんとか賃貸を借りれても、こんな環境の良いところで老後を過ごしたいので、ここは頑張るべきだろうか。
まずは、ローンの審査が降りるかが問題だが。
仕事はなくても、海外の市場や為替等のデータのコンピュータへの入力は続けなくてはならない。平均値や偏差等のデータが狂ってくる為。
昨日、オーディオシステムのスピーカーをJBLのモニターに入れ替えた。その仕事で腰がずっと痛んでいた。
音を聴いてがっかり、全く、クラシック向きではない。特に最新の古楽器の音色が駄目。古いアメリカのシカゴシンフォニーとかボストンシンフォニー等の演奏は、面白く再生される。
ジャズをかけると俄然、冴えてくる。特にシンバルの音なんか凄い。ペットのミュートやトロンボーンのワウワウなんかも面白い。ベースの音は物足りない。
午後からは、先日、不動産屋にクルマで連れていってもらった物件について駅から実際に歩いてみることにする。鈴蘭台についたら、もう4時30分。空気がヒンヤリとしている。その後、梅田に出てきたが、気温差5~6℃位あるのでは。
実際にあるいてみて、今の自宅の場所よりも坂は少ないが、それでも傾斜はあり、大体25分位かかった。(途中写真等撮影しながらなので、余計に時間がかかる。)付近には、神戸親和女子大や中学校、小学校、幼稚園、兵庫商業高校等、幼児教育から最高学府まで全て学校が揃っている。今日、見に行った家も校庭の裏側であることは話した通り。
今日は、お盆休みの人が多く、僕が、家を撮影していると、むかいがわの方が犬(大きな奴)の散歩に行く途中なので目があってしまった。ドキドキしながら頭を下げた。
その時悟った。「僕は引きこもり症なのにご近所つき合いやっていけるだろうか。」
ここの地域は、自然には、恵まれすぎる程、恵まれているので、居住者の表情も明るく、人間的な余裕がある感じ。家並みもそうだが、今までの家に比べて1~2クラス上の階層の人達が住んでいるようだ。
僕が買う予定(かな)の家は、襤褸家でおとぎ話に「古家の漏りほど恐い物はない。」いうが、その恐ろしさが現実化している家。
暫く撮影しながら駅に引き返したが、狭い山道なのにクルマを滅茶苦茶飛ばすので、歩行者は危ない。小さな子供を道路脇を歩かせるのは恐い感じ。
歩道の整備が遅れている県として、奈良県が挙げられるが、兵庫県もついで酷い。京都とか滋賀とかの住民の人がみたら、よくこのまま放置しているなぁという感じ。
公園も子供の飛び出し防止の為に2重の囲いになっている。最近、クルマに乗っていないから判らないが、隘路の通過とか行き違い等で徐行しなければならないということやはみだし禁止の2重線を無視する様なことが当然の様に行われているのに平気なんだろうか。
はみ出し禁止については、最近の馬鹿でかいクルマではみ出さずに走行することは、不可能なので、こんなクルマを製造販売している自動車メーカーにも責任がありそうだ。
クルマは、鈴鹿サーキットやF1だけで十分だ。
徒歩で25分かかるので、自転車の利用も考えたが、危険なのでやはり、自動車かもしくは徒歩ということになるようだ。今回みた家にも車庫があるが、クルマで駅までいく人が多いようだ。駐車場は、結構、ある方なので困らないということなのだろうか。
往復50分間歩いて足が棒になった。1日約7000歩が稼げるので、日本列島縦断の達成時期が早まるか。
それよりも呆れたのは、電車の乗車時間で、鈴蘭台から阪急梅田まで特急で約1時間。つまり大阪までは、1時間30分もかかってしまうことになる。神戸までは、1時間以内で行ける。
住環境をとるか、それとも便利さをとるかということだが、何よりも、私に採っては、予算の問題がある。
ボーナス減額、会社の昨年度末決算をみても売上高が5%程度減少しているので、このままでは、ローンの査定も通らず、貯金も結局、なんやかやで浪費してしまって、そうなると家を買うチャンス等二度とないだろう。
家賃やマンション維持費、管理費、修繕費を支払うだけの経済的余裕の無い老後の暮らしを守る為に、一戸建てを買わないと、どうにもならない。
また、なんとか賃貸を借りれても、こんな環境の良いところで老後を過ごしたいので、ここは頑張るべきだろうか。
まずは、ローンの審査が降りるかが問題だが。
1.物まなびのすぢ ― 2009/08/13 22:46
今日は、昨日歩きすぎて、足が痛むので、家に居り、講談社文庫 本居宣長「うひ山ぶみ」を読み始めた。
だんだんブログのネタもなくなり、ツマラナイと言われる様になってきたので、これを順々に勝手な注釈を加えていくことで記事の穴埋めにしたい。
1.物まなびのすぢ
①世に物まなびのすぢ、しなじな有りて、一やうならず。
ここでいう、「すぢ」とは、なんだろうか。これは、分類、体系のことである。古楽(国学)という比較的狭隘な学問分野さえ、多様であり、一言では言い表せないものであると宣長は、指摘している。
面白いのは、「うひの山ふみ」を始めるに当たって宣長は、「すぢ」について論じるところから始めている。つまり、「学問は体系から出発するものであり、全体の構成を俯瞰しなければ、枝葉末節のみを弄くっていても、何も理解出来ないことを示そうとしている。
宣長、以前の和歌、古典、史書についての「学び」は枝葉末節の積み重ねが、堆積していくやり方であったが、宣長に近い時期の塙保己一の群書類従にみられる様に、体系的、分類的に資料文献をみていこうとする気風が生まれた時代であり、宣長のこの言葉にもその気概がみられる。
②そのしなじなをいはば、まづ神代紀をむねとたてて、道をもはらと学ぶあり。
まず、その中で、一番重要なのは、いうまでもなく、古事記、日本書記他の日本の神代を扱った書物を学ぶ事で、これは、「道」である。つまり、ただ単に研究というよりも、「道を究める」という精神的修練が大切であるとしている。
私が考えるところでは、現代日本の学問は、人文学にみられる様に多種多様の寄せ集めとなっているが、体系としてまとまるには、いたらず、結局、烏合の衆の寄せ集めになってしまう。今の民俗学等がその最たるものであろう。
ここには、「道」の精神に欠けている。
「道」を進む、極めるだけではなくて、師匠から子弟、更にその子弟から孫弟子へと連綿と伝えられるものであり、それが、国学(国文学)の歴史でもあるし、目的でもある。源氏物語の研究も旧帝國大学教授から高等学校の教員に至るまで、「道」として伝えられてきたものだと私は考えている。
③これを神学といひ、その人と神道者といふ。
話はややぶれたが、神代紀を専ら学び「道」として極める人は、「神道者」と言われる。「神道者」は、宗教者であるが、現代の宮司、神職とは異なり、新たな「真実」を究めようとする態度がある点が異なっている。単なる儀式の伝承者ではない。
④また、有職・儀式・律令などをむねとして学ぶあり。
⑤また、もろもろの故実・装束・調度などの事をむねと学ぶあり。これらを有職の学といふ。
有職故実を学ぶということは、江戸時代においては、ある意味伝統文化の実践であり、実用でもあった。だから、近代以降の我々が文化史という一言で片付けるこの分野は、国学、神学を実際の儀式として、正しく神道者として「生きて」、実践していく手段であったので、単なる知識の集成ではない。
⑥また、上は六国史其の外のいにしへ文(古書)をはじめ後世の書共まで、いづれのすぢによるともなくてまなぶもあり。
⑦このすぢの中にも、猶、分けていはば、しなじな有るべし。
これは、書誌学のことを示している。書誌学という言葉は現在はなかったが、江戸寛永期以降の出版文化隆盛により、あらゆる古典籍が印刷、出版される様になり、巷の者どもでも容易に手に触れることが出来る様になった。図書が一般に流通する様になり、「本の分類、調査」が学びの「すぢ」として重要になっていく。
⑧また、歌の学び有り。それにも、歌をのみよむと、ふるき歌集・物語書などを解き明らむるとの二やうあり。
近代以前の古典(国文研究)については、歌学等、実際の歌会や俳諧連歌の実践になる知識を得る為の研究と、あるいは、現代の国文学者がやっている様に、古い時代の作品に注釈、考証を加える研究があることを示している。
定家卿の時代くらいまでは、歌の学びの道は、一筋であった。しかし、六条派の歌学が台頭し、これらとの論争が激化する中で、やがて、歌論に「勝つ」為のディベートの根拠となる知識としての平安朝以前の物語や和歌が重要視される様になっていく。
こでは、宣長は、どの様な「すぢ」が正しいのかは述べていないが、おそらく、これから、この書物を読み進むことで明らかにされていくのだろう。
こんな訳で、「物まなびのすぢ」の段が終わる訳だが、宣長が非常に客観的に当時の古典研究の状況を把握していたことが判り興味深い。「大和魂」や「もののあはれ」等の精神論的な側面で捉えられてきた宣長であるが、ある意味、即物、唯物的な見方をも有していたことがここから推察出来るのである。
写真は、旧宅「鈴屋」の内部から宣長の視線を再現したもの。
だんだんブログのネタもなくなり、ツマラナイと言われる様になってきたので、これを順々に勝手な注釈を加えていくことで記事の穴埋めにしたい。
1.物まなびのすぢ
①世に物まなびのすぢ、しなじな有りて、一やうならず。
ここでいう、「すぢ」とは、なんだろうか。これは、分類、体系のことである。古楽(国学)という比較的狭隘な学問分野さえ、多様であり、一言では言い表せないものであると宣長は、指摘している。
面白いのは、「うひの山ふみ」を始めるに当たって宣長は、「すぢ」について論じるところから始めている。つまり、「学問は体系から出発するものであり、全体の構成を俯瞰しなければ、枝葉末節のみを弄くっていても、何も理解出来ないことを示そうとしている。
宣長、以前の和歌、古典、史書についての「学び」は枝葉末節の積み重ねが、堆積していくやり方であったが、宣長に近い時期の塙保己一の群書類従にみられる様に、体系的、分類的に資料文献をみていこうとする気風が生まれた時代であり、宣長のこの言葉にもその気概がみられる。
②そのしなじなをいはば、まづ神代紀をむねとたてて、道をもはらと学ぶあり。
まず、その中で、一番重要なのは、いうまでもなく、古事記、日本書記他の日本の神代を扱った書物を学ぶ事で、これは、「道」である。つまり、ただ単に研究というよりも、「道を究める」という精神的修練が大切であるとしている。
私が考えるところでは、現代日本の学問は、人文学にみられる様に多種多様の寄せ集めとなっているが、体系としてまとまるには、いたらず、結局、烏合の衆の寄せ集めになってしまう。今の民俗学等がその最たるものであろう。
ここには、「道」の精神に欠けている。
「道」を進む、極めるだけではなくて、師匠から子弟、更にその子弟から孫弟子へと連綿と伝えられるものであり、それが、国学(国文学)の歴史でもあるし、目的でもある。源氏物語の研究も旧帝國大学教授から高等学校の教員に至るまで、「道」として伝えられてきたものだと私は考えている。
③これを神学といひ、その人と神道者といふ。
話はややぶれたが、神代紀を専ら学び「道」として極める人は、「神道者」と言われる。「神道者」は、宗教者であるが、現代の宮司、神職とは異なり、新たな「真実」を究めようとする態度がある点が異なっている。単なる儀式の伝承者ではない。
④また、有職・儀式・律令などをむねとして学ぶあり。
⑤また、もろもろの故実・装束・調度などの事をむねと学ぶあり。これらを有職の学といふ。
有職故実を学ぶということは、江戸時代においては、ある意味伝統文化の実践であり、実用でもあった。だから、近代以降の我々が文化史という一言で片付けるこの分野は、国学、神学を実際の儀式として、正しく神道者として「生きて」、実践していく手段であったので、単なる知識の集成ではない。
⑥また、上は六国史其の外のいにしへ文(古書)をはじめ後世の書共まで、いづれのすぢによるともなくてまなぶもあり。
⑦このすぢの中にも、猶、分けていはば、しなじな有るべし。
これは、書誌学のことを示している。書誌学という言葉は現在はなかったが、江戸寛永期以降の出版文化隆盛により、あらゆる古典籍が印刷、出版される様になり、巷の者どもでも容易に手に触れることが出来る様になった。図書が一般に流通する様になり、「本の分類、調査」が学びの「すぢ」として重要になっていく。
⑧また、歌の学び有り。それにも、歌をのみよむと、ふるき歌集・物語書などを解き明らむるとの二やうあり。
近代以前の古典(国文研究)については、歌学等、実際の歌会や俳諧連歌の実践になる知識を得る為の研究と、あるいは、現代の国文学者がやっている様に、古い時代の作品に注釈、考証を加える研究があることを示している。
定家卿の時代くらいまでは、歌の学びの道は、一筋であった。しかし、六条派の歌学が台頭し、これらとの論争が激化する中で、やがて、歌論に「勝つ」為のディベートの根拠となる知識としての平安朝以前の物語や和歌が重要視される様になっていく。
こでは、宣長は、どの様な「すぢ」が正しいのかは述べていないが、おそらく、これから、この書物を読み進むことで明らかにされていくのだろう。
こんな訳で、「物まなびのすぢ」の段が終わる訳だが、宣長が非常に客観的に当時の古典研究の状況を把握していたことが判り興味深い。「大和魂」や「もののあはれ」等の精神論的な側面で捉えられてきた宣長であるが、ある意味、即物、唯物的な見方をも有していたことがここから推察出来るのである。
写真は、旧宅「鈴屋」の内部から宣長の視線を再現したもの。
2.「みづから思ひよれる方」 ― 2009/08/14 23:15
2.「みづから思ひよれる方」
「うひ山ぶみ」第2段は、前の「すぢ」についての続きであるが、この「すぢ」と学ぶ物の志向方向のベクトルである「思ひよれる方」の関係について、宣長は述べている。
簡単に言えば、「志望」、「志願」であるが、佛教大学通信教育部は、無試験で入学出来るが、一応、申込書に「みづから思ひよれる方」についての100字程度の作文を書かせられるし、3回生になれば、論文テーマの調査票にもこの「思ひよれる方」について書く必要がある。
特に3年次編入の通信生がいきなり、「論文テーマ」といっても、「思ひよれる方が定まっていないので、困惑するし、論文草稿許可が下りてからテーマを変えるというケースも出てくるのである。
「すぢ」から「思ひよれる方」を見いだすのが、研究・学習の第1歩なのである。
①大かた件のしなじな有りて、おのおの好むすぢによりてまなぶに、又、おのおのその学びやうの法も、教ふる師の心々、まなぶ人の心々にてさまざまあり。
大体、学習を志すものは、前回示した様なテーマ(学問分野)を「思ひよれる方」(志望・志向)によって、選択して学ぶが、人それぞれの心(考え方、ポリシー)が、パーソナリティによって異なっているので、指導を受ける教師の考え方もパーソナリティによって様々なので、その研究、学習の方法は、多種多様になってしまう。
つまり、教授・教師の研究指導についても、人それぞれ考え方によって異なるし、学生の考え方や興味を持つ方向も異なっているのに、研究指導を行わなければ、ならない難しさをここでは指摘しているのである。
②かくて学問に心ざして入りそむる人、はじめよりみづから思ひよれるすぢありて、その学びやうもみづからはからふも有るを、又さやうにとり分きてそれを思ひよれるすぢもなく、まなびやうもみづから思ひよれるかたなきは、物しり人につきて、「いづれのすぢに入りてかやからん。又、うひ学びの輩のまなびやうは、いづれの書よりまづ見るべきぞ」など問ひ求む、これつねの事なるが、まことに然あるべきことにて、その学びのしなを正し、まなびやうの法をも正して、ゆくさきよこさまなるあしき方に落ちざるやう。又、其業のはやく成るべきやう、すべて功(いさを)多かるべきやうを、はじめより、よくしたためて入いらもほしわざ也。
最初から、研究テーマや方向性、興味の対象が決まっている人は、自己能力で、その研究、学習方法も見いだして、進むことが出来るが、一方で、そんな研究テーマや方向性、興味が最初から決まっていない人は、物知り人(教師やそのすぢに詳しい人)の教えを受けて、
「どの様な分野、方法を選んだら宜しいでしょうか。又、その入門書は、どんなものがお薦めですか。」等を質問して求めることは、世の中の常である。
これは、本当にもっともなことであり、その学習や研究に取り組み態度や学習や研究方法そのものを矯正して、間違った方向に陥らないように方向修正を行い、又、研究や学習を進めて大きな成果を早い段階で得ることが出来る様な効率的な研究、学習方法を知っておきたいものである。
結局、多くの学生がテーマを見いだすことに苦労するが、その様な人は、良い教師について、その研究テーマ、研究方針、研究方法を早い段階で身につけることの大切さをここでは、述べている。
③同じく精力を用ひながらも、そのすぢそのまなぶやうによりて得失あるべきこと也。
研究方法次第で、同じ労力、時間を消費しても、成果に大きな差が出てくるのである。
④然はあれども、まづかの学びのしなじなは、他よりしひてそれをとはいひがたし。大抵みずから思ひよれる方にまかすべき也。
しかし、そうであっても、研究や学習方法は他人から強制されるものではなくて、大抵は、「思ひよれる方」に従って自発的に進めなければならないのである。
私の経験では、興味や学習方法は、結局は、教えられた通りやるものではなくて、早く、「思ひよれるすぢ」を見いだして、自律的に進めていかなければ、学問や研究そのものへの興味さえも失ってしまうものである。
⑤いかに初心なればとても、学問にもこころざすほどのものは、むげに小児の心のやうにはあらねば、ほどほどにみづから思ひよれるすぢは必ずあるものなり。
学問を志す者はもう子供ではないのだから、それぞれにおいて、自らの志望、志向は必ず見つかるものである。
⑥又、面々好むかたと好まぬ方ども有り、又、生まれつき得たる事と得ぬ事ども有る物なるを、好まぬ事得ぬ事をしては、同じやうにつとめても、功を得ることすくなし。
生まれながらに人は好き嫌いがあり、更に才能がある分野と無い分野があるので、嫌いなこと、不得手な事を、その分野が好きな人、才能がある人と一緒に努力しても成果を得ることは非常に少ないのである。
まさに私もその様な勝手な人間だと思う。しかし、現代社会は、その様な勝手を許さない。学歴や資格を得る為に履修単位が必要だから、渋々、嫌いでも不得手でも、その講義を受けたり、卒論に取り組んだりしている学生達がいかに多いことか。
⑦又、いづれのしなにもせよ、学びやうの次第も、一わたりの理によりて「云々してよろし」とさして教へんは、やすきことなれども、そのさして教へたるごとくにして、果たしてよきものならんや、又思ひの他にさては、あしき物ならんや、実にはしりがたきことなれば、これもしひて定めがたきわざにして、実はただ其人の心まかせにしてよき也。
又、どの様な学問分野にしても、研究方法について「1つの理想」のみが絶対であるとして教える。機械的に教えることは簡単であるが、そんな指導方法を採って本当に良いものだろうか。教師にとっては、それが理想的な方法にとっても学生や生徒にとっては、非常にやりにくく、悪い結果を生む事になるかもしれないのである。だから、研究指導は、実際には、本人の意思を尊重して行われるべきなのである。
なにか、現代の佛大の修論中間発表会とか、大学での現場をみながら、宣長が文章を書いている様な気がする。
博士課程の学生ですら、「こいつ、「思ひよれる方」か何か、本当にあるのか。」と思うような程度の低い研究発表が全体の8割方を占めており、国文近世文学のN先生の毒舌がそういった学生を叩きのめしていった。
こんな風に、覇気や自主性の無い学生が多いことから、論文テーマを提出させて、先行研究がどうのこうのしている内に、自分の姿を失ってしまうのである。
やがて、大学自体に興味を無くしてしまって、中途退学につながっていく。私も関大の時は、その様な弊害の中で受動的な学習態度であったので、ほとんど何も得るものはなかった。
佛教大学の通信大学院に入って、研究テーマから日常的な学習態度、研究方法まで、自分で開拓、開発する面白さ、楽しさを得たから今の自分があるのだと思っている。
写真は宣長の旧宅の書斎に上がる階段。
「うひ山ぶみ」第2段は、前の「すぢ」についての続きであるが、この「すぢ」と学ぶ物の志向方向のベクトルである「思ひよれる方」の関係について、宣長は述べている。
簡単に言えば、「志望」、「志願」であるが、佛教大学通信教育部は、無試験で入学出来るが、一応、申込書に「みづから思ひよれる方」についての100字程度の作文を書かせられるし、3回生になれば、論文テーマの調査票にもこの「思ひよれる方」について書く必要がある。
特に3年次編入の通信生がいきなり、「論文テーマ」といっても、「思ひよれる方が定まっていないので、困惑するし、論文草稿許可が下りてからテーマを変えるというケースも出てくるのである。
「すぢ」から「思ひよれる方」を見いだすのが、研究・学習の第1歩なのである。
①大かた件のしなじな有りて、おのおの好むすぢによりてまなぶに、又、おのおのその学びやうの法も、教ふる師の心々、まなぶ人の心々にてさまざまあり。
大体、学習を志すものは、前回示した様なテーマ(学問分野)を「思ひよれる方」(志望・志向)によって、選択して学ぶが、人それぞれの心(考え方、ポリシー)が、パーソナリティによって異なっているので、指導を受ける教師の考え方もパーソナリティによって様々なので、その研究、学習の方法は、多種多様になってしまう。
つまり、教授・教師の研究指導についても、人それぞれ考え方によって異なるし、学生の考え方や興味を持つ方向も異なっているのに、研究指導を行わなければ、ならない難しさをここでは指摘しているのである。
②かくて学問に心ざして入りそむる人、はじめよりみづから思ひよれるすぢありて、その学びやうもみづからはからふも有るを、又さやうにとり分きてそれを思ひよれるすぢもなく、まなびやうもみづから思ひよれるかたなきは、物しり人につきて、「いづれのすぢに入りてかやからん。又、うひ学びの輩のまなびやうは、いづれの書よりまづ見るべきぞ」など問ひ求む、これつねの事なるが、まことに然あるべきことにて、その学びのしなを正し、まなびやうの法をも正して、ゆくさきよこさまなるあしき方に落ちざるやう。又、其業のはやく成るべきやう、すべて功(いさを)多かるべきやうを、はじめより、よくしたためて入いらもほしわざ也。
最初から、研究テーマや方向性、興味の対象が決まっている人は、自己能力で、その研究、学習方法も見いだして、進むことが出来るが、一方で、そんな研究テーマや方向性、興味が最初から決まっていない人は、物知り人(教師やそのすぢに詳しい人)の教えを受けて、
「どの様な分野、方法を選んだら宜しいでしょうか。又、その入門書は、どんなものがお薦めですか。」等を質問して求めることは、世の中の常である。
これは、本当にもっともなことであり、その学習や研究に取り組み態度や学習や研究方法そのものを矯正して、間違った方向に陥らないように方向修正を行い、又、研究や学習を進めて大きな成果を早い段階で得ることが出来る様な効率的な研究、学習方法を知っておきたいものである。
結局、多くの学生がテーマを見いだすことに苦労するが、その様な人は、良い教師について、その研究テーマ、研究方針、研究方法を早い段階で身につけることの大切さをここでは、述べている。
③同じく精力を用ひながらも、そのすぢそのまなぶやうによりて得失あるべきこと也。
研究方法次第で、同じ労力、時間を消費しても、成果に大きな差が出てくるのである。
④然はあれども、まづかの学びのしなじなは、他よりしひてそれをとはいひがたし。大抵みずから思ひよれる方にまかすべき也。
しかし、そうであっても、研究や学習方法は他人から強制されるものではなくて、大抵は、「思ひよれる方」に従って自発的に進めなければならないのである。
私の経験では、興味や学習方法は、結局は、教えられた通りやるものではなくて、早く、「思ひよれるすぢ」を見いだして、自律的に進めていかなければ、学問や研究そのものへの興味さえも失ってしまうものである。
⑤いかに初心なればとても、学問にもこころざすほどのものは、むげに小児の心のやうにはあらねば、ほどほどにみづから思ひよれるすぢは必ずあるものなり。
学問を志す者はもう子供ではないのだから、それぞれにおいて、自らの志望、志向は必ず見つかるものである。
⑥又、面々好むかたと好まぬ方ども有り、又、生まれつき得たる事と得ぬ事ども有る物なるを、好まぬ事得ぬ事をしては、同じやうにつとめても、功を得ることすくなし。
生まれながらに人は好き嫌いがあり、更に才能がある分野と無い分野があるので、嫌いなこと、不得手な事を、その分野が好きな人、才能がある人と一緒に努力しても成果を得ることは非常に少ないのである。
まさに私もその様な勝手な人間だと思う。しかし、現代社会は、その様な勝手を許さない。学歴や資格を得る為に履修単位が必要だから、渋々、嫌いでも不得手でも、その講義を受けたり、卒論に取り組んだりしている学生達がいかに多いことか。
⑦又、いづれのしなにもせよ、学びやうの次第も、一わたりの理によりて「云々してよろし」とさして教へんは、やすきことなれども、そのさして教へたるごとくにして、果たしてよきものならんや、又思ひの他にさては、あしき物ならんや、実にはしりがたきことなれば、これもしひて定めがたきわざにして、実はただ其人の心まかせにしてよき也。
又、どの様な学問分野にしても、研究方法について「1つの理想」のみが絶対であるとして教える。機械的に教えることは簡単であるが、そんな指導方法を採って本当に良いものだろうか。教師にとっては、それが理想的な方法にとっても学生や生徒にとっては、非常にやりにくく、悪い結果を生む事になるかもしれないのである。だから、研究指導は、実際には、本人の意思を尊重して行われるべきなのである。
なにか、現代の佛大の修論中間発表会とか、大学での現場をみながら、宣長が文章を書いている様な気がする。
博士課程の学生ですら、「こいつ、「思ひよれる方」か何か、本当にあるのか。」と思うような程度の低い研究発表が全体の8割方を占めており、国文近世文学のN先生の毒舌がそういった学生を叩きのめしていった。
こんな風に、覇気や自主性の無い学生が多いことから、論文テーマを提出させて、先行研究がどうのこうのしている内に、自分の姿を失ってしまうのである。
やがて、大学自体に興味を無くしてしまって、中途退学につながっていく。私も関大の時は、その様な弊害の中で受動的な学習態度であったので、ほとんど何も得るものはなかった。
佛教大学の通信大学院に入って、研究テーマから日常的な学習態度、研究方法まで、自分で開拓、開発する面白さ、楽しさを得たから今の自分があるのだと思っている。
写真は宣長の旧宅の書斎に上がる階段。
「白鳥説話」 ― 2009/08/15 10:38
「白鳥説話」
毎年、「敗戦の日」には、ワーグナーのパルシファルやローエングリンを聞く。
「聖なる愚者」パルシファルの清透な終末感のイメージは、この日にしみじみと聞くのに相応しい。
毒々しい戦いと色欲のドラマも、「聖なる愚者」によって真っ白に浄化されていく。
「浄化」というイメージを、ワーグナーにみられるゲルマン説話では、「白鳥」の美しさになぞらえている。
古事記の中で、「英雄の死の象徴」としての白鳥の昇天説話は、最も美しい部分である。高校時代の古典の時間に、この部分を授業で習ったが、朗読をされている先生の声が感極まって、声が出なくなってしまったことを記憶している。この先生の授業は独特で、古典をただ読む(音読)だけで、別に現代語訳とか、注釈とか、文法の解説等、全くされないのに、先生の朗読に聞き入っている内、ネイティブランゲージとして、古典の文章が徐々に理解出来る様になっていくのである。
話は戻るが、ワーグナーのローエングリンでは、白鳥の王子が登場するが、劇的な最後という訳ではない。神々の黄昏では、ワルハラの城が燃えて、神々のエゴイズムの悲劇が終わりを告げ、復しゅうに燃える悪者が水に飲まれて死ぬが、白鳥の昇天・死に見られるような清透な情景を持った悲劇という表現ではない。
一方、古事記描かれた倭建命の最後の情景は、もっとずっと美しく、日本民族の心の気高さを描いている。
ここに倭に坐す后等また皇子達、諸下り至りて、御陵をつくり、すなはち、其地のんづき田に匍匐廻りて哭きまして歌ひたまひしく、
なづき田の稲幹に 稲幹に 匍ひ廻ろふ 野老葛
とうたひたまひき。ここに八尋白智鳥に化りて、天に翔りて濱に向きて飛び行でましき。ここにその后また御子達、その小竹の刈杙に足きり破れども、その痛きを忘れて、哭きて追ひたまひき、この時に歌ひたまひしく・・・・
白鳥のみささぎの起こりを描いた部分であるが、同時に古事記という物語作者の倭建命への哀悼の文章である。
「哭きて」とあるが、中国の葬制に関しての資料によれば、中国では、帝王や英雄が亡くなった時には、その葬儀で「泣く」という行為が非常に重要であった。「哭」は、その中で、最も重みを持った「泣き方」であり、地面に腹ばい、頭を打ち付けて、それこそ血が出るまで打ち付けて高らかに鳴き声を挙げて、みずからも死んでまで付き従おうという強い意思の表現である。
面白いのは、倭建命の妻に対する言葉は、描かれず、それよりも、死の直前に逢瀬をもったミヤズ姫のことを臨終の時に詠んだ、
「嬢子の床の邊に 我が置きし つるぎの太刀 その太刀はや」という象徴的な歌が詠まれる。
この白鳥の場面に出てくる后達についての描写や倭建命の「言葉」がみられないのは、何故だろうか。
「単なる白鳥説話なんだからさ。」と言われてしまえばどうしようも無いが、ここに倭建尊の生き方の2面性がうかがわれるのである。
帝に命じられて各地の征討に赴く尊は徐々に疲れて身体も弱ってくる。その時に、「ひさかたの天の香具山 利鎌に さ渡る頸」という和歌を詠むが、これは、自らの死を悟った諦観の歌であると同時に、オオヤケの立場から、本来の人間の立場に帰ったということだろう。
倭建尊は、残念ながら実在しなかった可能性が高いそうである。
帝(大和朝廷)の名で各地に征討に赴き、大勢のものが戦死、あるいは、疲れて亡くなっていった大勢の英霊の御霊の象徴として、この物語の最後の場面が描かれているのであろう。
スメラミコトの権威が固まったこの時期、天皇への絶対服従という行為の中で、潔く死んでいくという美談と白鳥に象徴される美しい日本人の本来の魂が昇華される有様を同時に描くことで、この物語の悲劇性を一層、強めているのだと私は考える。
毎年、「敗戦の日」には、ワーグナーのパルシファルやローエングリンを聞く。
「聖なる愚者」パルシファルの清透な終末感のイメージは、この日にしみじみと聞くのに相応しい。
毒々しい戦いと色欲のドラマも、「聖なる愚者」によって真っ白に浄化されていく。
「浄化」というイメージを、ワーグナーにみられるゲルマン説話では、「白鳥」の美しさになぞらえている。
古事記の中で、「英雄の死の象徴」としての白鳥の昇天説話は、最も美しい部分である。高校時代の古典の時間に、この部分を授業で習ったが、朗読をされている先生の声が感極まって、声が出なくなってしまったことを記憶している。この先生の授業は独特で、古典をただ読む(音読)だけで、別に現代語訳とか、注釈とか、文法の解説等、全くされないのに、先生の朗読に聞き入っている内、ネイティブランゲージとして、古典の文章が徐々に理解出来る様になっていくのである。
話は戻るが、ワーグナーのローエングリンでは、白鳥の王子が登場するが、劇的な最後という訳ではない。神々の黄昏では、ワルハラの城が燃えて、神々のエゴイズムの悲劇が終わりを告げ、復しゅうに燃える悪者が水に飲まれて死ぬが、白鳥の昇天・死に見られるような清透な情景を持った悲劇という表現ではない。
一方、古事記描かれた倭建命の最後の情景は、もっとずっと美しく、日本民族の心の気高さを描いている。
ここに倭に坐す后等また皇子達、諸下り至りて、御陵をつくり、すなはち、其地のんづき田に匍匐廻りて哭きまして歌ひたまひしく、
なづき田の稲幹に 稲幹に 匍ひ廻ろふ 野老葛
とうたひたまひき。ここに八尋白智鳥に化りて、天に翔りて濱に向きて飛び行でましき。ここにその后また御子達、その小竹の刈杙に足きり破れども、その痛きを忘れて、哭きて追ひたまひき、この時に歌ひたまひしく・・・・
白鳥のみささぎの起こりを描いた部分であるが、同時に古事記という物語作者の倭建命への哀悼の文章である。
「哭きて」とあるが、中国の葬制に関しての資料によれば、中国では、帝王や英雄が亡くなった時には、その葬儀で「泣く」という行為が非常に重要であった。「哭」は、その中で、最も重みを持った「泣き方」であり、地面に腹ばい、頭を打ち付けて、それこそ血が出るまで打ち付けて高らかに鳴き声を挙げて、みずからも死んでまで付き従おうという強い意思の表現である。
面白いのは、倭建命の妻に対する言葉は、描かれず、それよりも、死の直前に逢瀬をもったミヤズ姫のことを臨終の時に詠んだ、
「嬢子の床の邊に 我が置きし つるぎの太刀 その太刀はや」という象徴的な歌が詠まれる。
この白鳥の場面に出てくる后達についての描写や倭建命の「言葉」がみられないのは、何故だろうか。
「単なる白鳥説話なんだからさ。」と言われてしまえばどうしようも無いが、ここに倭建尊の生き方の2面性がうかがわれるのである。
帝に命じられて各地の征討に赴く尊は徐々に疲れて身体も弱ってくる。その時に、「ひさかたの天の香具山 利鎌に さ渡る頸」という和歌を詠むが、これは、自らの死を悟った諦観の歌であると同時に、オオヤケの立場から、本来の人間の立場に帰ったということだろう。
倭建尊は、残念ながら実在しなかった可能性が高いそうである。
帝(大和朝廷)の名で各地に征討に赴き、大勢のものが戦死、あるいは、疲れて亡くなっていった大勢の英霊の御霊の象徴として、この物語の最後の場面が描かれているのであろう。
スメラミコトの権威が固まったこの時期、天皇への絶対服従という行為の中で、潔く死んでいくという美談と白鳥に象徴される美しい日本人の本来の魂が昇華される有様を同時に描くことで、この物語の悲劇性を一層、強めているのだと私は考える。
3.「怠りてつとめざれば功はなし」 ― 2009/08/16 01:07
3.「怠りてつとめざれば功はなし」
最も、「うひ山ぶみ」では、多くの人々に引用されて来た章段である。
①詮ずるところ学問は、ただ年月長く倦まずおこたらずして、はげみつとむるぞ肝要にて、学ぶやうは、いかやうにてもよかるべく、さのみかかはるまじきこと也。
結局、学問は、どんな学び方でも良いから長い年月を絶え間なく、努力を続けることが最も重要である。(係り結びの用法が不適当な宣長らしからぬ文章だと思う。)
まぁ、当然のことである。長続きしようと思えば、自分に合ったやり方でしか、残っていかない。大学院で博士課程をおえても、スーパーのレジ打ち等の仕事に追われて、もう、学問も何もかも離れてしまっている人もいる。
大学在学中は、院を含めても精々10年位なのだが、その後、研究職につけないことも多く、その場合、諦めてしまって、すっかり怠惰になり、日常の暮らしに追われてしまうのが人の常であると思う。
②いかほど学びかたよくても、怠りてつとめざれば、功はなし。
先生が薦める様な学習方法でも、怠けて努力しなかったら全然効果はない。
僕の場合は、不謹慎だと思うが、テキストを寝転んで読んだり、電車の中で読んだり、気楽に出来る方法を選ぶことにしていたので、佛大通信のテキスト履修もなんとか続いたのだと思う。
③又、人々の才と不才とによりて、其功いたく異なれども、才・不才は生まれつきたることなれば、力に及びがたし。
人間の才能の有り無しで成果は大きく違ってくるが、これは、生まれつきなので、仕方がない。
④されど、大抵は、不才なる人といへども、おこたらずつとめだにすれば、それだけの功は有る物也。
しかしながら、才能が無い人でも、サボらず、努力をつづければ、それなりの成果を挙げることが出来る。
モーツアルトとサリエリの関係の様だ。実際には、凡才であったサリエリの方が、努力家であった様で、長生き出来たので、宮廷楽長にまでなることが出来た。モーツアルトは、30歳そこそこで、病死した後、貧民墓地に投げ込まれた。(映画で白い消毒用石灰をかけられている有様が目に浮かぶ。今でも鳥インフルエンザで殺処分された鶏の死骸には、石灰がかけられており、有効な消毒手段であったようだ。)
サリエリの様な才能がない人は、努力しても仕方がないと思う。
むしろ、才が発揮出来る分野にうつった方が、人生は幸せになれる筈だと私は思うが、そうでない人もいるようだ。
⑤又、晩学の人も、つとめはげめば、思ひの外、功をなすことあり。
佛大で最高齢で通信大学院で博士号を取得した方が、06年の3月に表彰を受けた。私もどうゆう訳か表彰されたので、側で、眺めていたが、晩年になると、つとめはげむこと自体が、生き甲斐になってくるので、功などどうでもよくなり、努力を続けるので、無欲による大きな成果だと思う。
功、功と言っている輩ほど、功をなさぬものだと思う。
⑥又、暇のなき人も、思ひの外、いとま多き人よりも功をなすもの也。
これも、通信生の為にある様な言葉だと思う。時間がないと時間を効率的に使う方法を習得することになる。
時間の大切さを知って、無駄を省く取捨選択の作業が必要になり、その選択の作業の中で、現在、学習している事項の中で、何が一番重要なのかを常に考え続けることになり、短時間だとかえって集中出来るので、質の高い学習・研究が出来ることになり、成果につながるのだと思う。
宣長自体の古典の研究も医者の副業として、晩年の学問として修得されたものであり、又、賀茂真淵とのたった1回のスクーリングと往復書簡による通信教育で行われたのである。
そういえば、学習会の時にも似たようなことをおっしゃられている先生がおられた様な気がする。
写真は、本来の鈴屋が建っていた跡。
最も、「うひ山ぶみ」では、多くの人々に引用されて来た章段である。
①詮ずるところ学問は、ただ年月長く倦まずおこたらずして、はげみつとむるぞ肝要にて、学ぶやうは、いかやうにてもよかるべく、さのみかかはるまじきこと也。
結局、学問は、どんな学び方でも良いから長い年月を絶え間なく、努力を続けることが最も重要である。(係り結びの用法が不適当な宣長らしからぬ文章だと思う。)
まぁ、当然のことである。長続きしようと思えば、自分に合ったやり方でしか、残っていかない。大学院で博士課程をおえても、スーパーのレジ打ち等の仕事に追われて、もう、学問も何もかも離れてしまっている人もいる。
大学在学中は、院を含めても精々10年位なのだが、その後、研究職につけないことも多く、その場合、諦めてしまって、すっかり怠惰になり、日常の暮らしに追われてしまうのが人の常であると思う。
②いかほど学びかたよくても、怠りてつとめざれば、功はなし。
先生が薦める様な学習方法でも、怠けて努力しなかったら全然効果はない。
僕の場合は、不謹慎だと思うが、テキストを寝転んで読んだり、電車の中で読んだり、気楽に出来る方法を選ぶことにしていたので、佛大通信のテキスト履修もなんとか続いたのだと思う。
③又、人々の才と不才とによりて、其功いたく異なれども、才・不才は生まれつきたることなれば、力に及びがたし。
人間の才能の有り無しで成果は大きく違ってくるが、これは、生まれつきなので、仕方がない。
④されど、大抵は、不才なる人といへども、おこたらずつとめだにすれば、それだけの功は有る物也。
しかしながら、才能が無い人でも、サボらず、努力をつづければ、それなりの成果を挙げることが出来る。
モーツアルトとサリエリの関係の様だ。実際には、凡才であったサリエリの方が、努力家であった様で、長生き出来たので、宮廷楽長にまでなることが出来た。モーツアルトは、30歳そこそこで、病死した後、貧民墓地に投げ込まれた。(映画で白い消毒用石灰をかけられている有様が目に浮かぶ。今でも鳥インフルエンザで殺処分された鶏の死骸には、石灰がかけられており、有効な消毒手段であったようだ。)
サリエリの様な才能がない人は、努力しても仕方がないと思う。
むしろ、才が発揮出来る分野にうつった方が、人生は幸せになれる筈だと私は思うが、そうでない人もいるようだ。
⑤又、晩学の人も、つとめはげめば、思ひの外、功をなすことあり。
佛大で最高齢で通信大学院で博士号を取得した方が、06年の3月に表彰を受けた。私もどうゆう訳か表彰されたので、側で、眺めていたが、晩年になると、つとめはげむこと自体が、生き甲斐になってくるので、功などどうでもよくなり、努力を続けるので、無欲による大きな成果だと思う。
功、功と言っている輩ほど、功をなさぬものだと思う。
⑥又、暇のなき人も、思ひの外、いとま多き人よりも功をなすもの也。
これも、通信生の為にある様な言葉だと思う。時間がないと時間を効率的に使う方法を習得することになる。
時間の大切さを知って、無駄を省く取捨選択の作業が必要になり、その選択の作業の中で、現在、学習している事項の中で、何が一番重要なのかを常に考え続けることになり、短時間だとかえって集中出来るので、質の高い学習・研究が出来ることになり、成果につながるのだと思う。
宣長自体の古典の研究も医者の副業として、晩年の学問として修得されたものであり、又、賀茂真淵とのたった1回のスクーリングと往復書簡による通信教育で行われたのである。
そういえば、学習会の時にも似たようなことをおっしゃられている先生がおられた様な気がする。
写真は、本来の鈴屋が建っていた跡。
太陽系をつくる 一気に30号分組み立て ― 2009/08/16 22:48
お盆休みも今日で終わり。結局、4日間の休みのうち、2日間は、いつもと同じ様に仕事をしてしまった。(在宅なので、休みと仕事とのケジメがない。)
最後の日にディアゴスティーニの「太陽系をつくる」が現在、30号まで出ていて、20号までの応募券を揃えると、景品がもらえるというので、来月末までで締め切りなので、まとめて作ってしまおうと思い立った。
さすがに30号まで積み上がると相当な高さになって置き場所にも困る様になっていたので、一気に組み立てる。
いつものことだが、「ディアゴスティーニさんなんとかしてよ!」ということで大変な量の包装材である。段ボールや、プラスティック(包装)で山の様になる。また、開封も大変手間がかかる。30号までの組み立てて4時間かかったが、大半は、開封とゴミ処理の作業(段ボールは細かな断片なので、紙のゴミの日に出すのは、めんどうくさいのでシュレッダーにかけていく。これが時間がかかる。)開封は、写真右上の様にプラパックに入っているが、一々、ハサミで丁寧に四隅を切り取っていかないとバラバラと開封後になくなっては困る部品が散らばることになる。
最初は慣れないので細かなネジの取り付けに手間取る。それでもどうにか、左上の地球までで1時間30分程度で完成。
組み立て作業は、クラシックカメラの分解と組み立てに似ていて、細かなネジ(6角レンチ用でしかもカメラの部品等に近い超小型ネジと小型な皿ネジ(十字溝)の組合せである。
このネジが慣れないうちは、6角レンチやドライバーから外れてポロポロ落ちて部屋の隅に転がる。
慌てて、カメラ分解用のシートを敷いて作業を始める。
①6角レンチ用の小型ネジは、最初から、ネジ穴に当てるとうまくねじ込めずに飛び散る原因になるので、最初にレンチの方にネジを填めてから、回転させながら取り付け穴に当てていくと簡単に確実に入っていく。(慎重に落ち着いて確実に作業を進める。)
②皿ネジは、プラスティックの部品にねじ込むタイプのネジだが、締めすぎるとバカになり厄介なので、締めすぎない様に注意。(1箇所、私は、締めすぎてしまって接着材を充填する羽目になった。)
③惑星(本体)の取り付けは、差し込み式だが、緩いので、ゴム系の接着材を使用した。これだと直ぐに外れるので、万が一の時には良い。間違っても瞬間接着剤を使用してはならない。
④組み上がるにつれて本体は、不安定になるので、保持に注意すること。通常の建物等の模型と違って最上階から組みあげていくので、こんなことになる。私の場合は、太陽から垂直に伸びている軸を天体望遠鏡の赤道儀の重りを利用して、その穴に差し込んで止めている。本体よりも重いので、良く安定する。保持の工夫が必要である。
以上の4点に注意して行けば、簡単である。ロボットの時は、頭とか胴体とか腕とか、基盤とか配線、モーターと様々な難しい作業で飽きなかったが、今回は、ひたすら単調・単純なネジ止めの作業である。
1つの惑星の公転のギアの組合せは、右上の6つの部品で構成されている。この組み方、ネジ止めの順序は、太陽、水星、金星は異なるが、地球以下は、全て同じで、ギア比が異なるだけなので、全く同じ作業である。この為、木星とか土星とか全然、説明をみなくても組み上がってしまった。
また、組みあげる時も、1つの惑星で、この6個が揃うまで待ってから組み立てを進めれば、部品保管中の紛失事故が防げる。
組み立ててみて、この太陽系儀は、初心者クラスのものだと判って少しがっかりした。
部品はしっかりしているが、例えば、地球以外の惑星の自転を再現していないし、一番がっかりなのは、ガリレオ衛星や火星、土星の衛星等がただ単に棒で固定されているだけで、それ自体の回転をみることが出来ないこと。
中学校の時に、もっと大型の太陽系儀をみる経験があったが、それは素晴らしく、当然、惑星は公転するし、火星、木星、土星等も自転する上にガリレオ衛星も木星の周回するので、非常に面白かった。
これは、ただ単に、太陽の回りをぐるぐる回るだけである。
土星等の惑星の個体の模型細工が程度がイマイチという点である。こんなものが出来上がって販売されているのかどうか判らないが、精々5~6万円位の商品である。雑誌付きであるが、9万円を越えてくると、ロボットといい勝負で、買わなかった方が良かったかも。
こんなキットがあるのならば、ゼンマイ振り子時計なんかの模型のキット等発売して欲しいと思う。ギアの組み立てなんか、面白いと思う。
トホホ、だが、ここまで来てしまったら、最後まで走るしかないようだ。
最後の日にディアゴスティーニの「太陽系をつくる」が現在、30号まで出ていて、20号までの応募券を揃えると、景品がもらえるというので、来月末までで締め切りなので、まとめて作ってしまおうと思い立った。
さすがに30号まで積み上がると相当な高さになって置き場所にも困る様になっていたので、一気に組み立てる。
いつものことだが、「ディアゴスティーニさんなんとかしてよ!」ということで大変な量の包装材である。段ボールや、プラスティック(包装)で山の様になる。また、開封も大変手間がかかる。30号までの組み立てて4時間かかったが、大半は、開封とゴミ処理の作業(段ボールは細かな断片なので、紙のゴミの日に出すのは、めんどうくさいのでシュレッダーにかけていく。これが時間がかかる。)開封は、写真右上の様にプラパックに入っているが、一々、ハサミで丁寧に四隅を切り取っていかないとバラバラと開封後になくなっては困る部品が散らばることになる。
最初は慣れないので細かなネジの取り付けに手間取る。それでもどうにか、左上の地球までで1時間30分程度で完成。
組み立て作業は、クラシックカメラの分解と組み立てに似ていて、細かなネジ(6角レンチ用でしかもカメラの部品等に近い超小型ネジと小型な皿ネジ(十字溝)の組合せである。
このネジが慣れないうちは、6角レンチやドライバーから外れてポロポロ落ちて部屋の隅に転がる。
慌てて、カメラ分解用のシートを敷いて作業を始める。
①6角レンチ用の小型ネジは、最初から、ネジ穴に当てるとうまくねじ込めずに飛び散る原因になるので、最初にレンチの方にネジを填めてから、回転させながら取り付け穴に当てていくと簡単に確実に入っていく。(慎重に落ち着いて確実に作業を進める。)
②皿ネジは、プラスティックの部品にねじ込むタイプのネジだが、締めすぎるとバカになり厄介なので、締めすぎない様に注意。(1箇所、私は、締めすぎてしまって接着材を充填する羽目になった。)
③惑星(本体)の取り付けは、差し込み式だが、緩いので、ゴム系の接着材を使用した。これだと直ぐに外れるので、万が一の時には良い。間違っても瞬間接着剤を使用してはならない。
④組み上がるにつれて本体は、不安定になるので、保持に注意すること。通常の建物等の模型と違って最上階から組みあげていくので、こんなことになる。私の場合は、太陽から垂直に伸びている軸を天体望遠鏡の赤道儀の重りを利用して、その穴に差し込んで止めている。本体よりも重いので、良く安定する。保持の工夫が必要である。
以上の4点に注意して行けば、簡単である。ロボットの時は、頭とか胴体とか腕とか、基盤とか配線、モーターと様々な難しい作業で飽きなかったが、今回は、ひたすら単調・単純なネジ止めの作業である。
1つの惑星の公転のギアの組合せは、右上の6つの部品で構成されている。この組み方、ネジ止めの順序は、太陽、水星、金星は異なるが、地球以下は、全て同じで、ギア比が異なるだけなので、全く同じ作業である。この為、木星とか土星とか全然、説明をみなくても組み上がってしまった。
また、組みあげる時も、1つの惑星で、この6個が揃うまで待ってから組み立てを進めれば、部品保管中の紛失事故が防げる。
組み立ててみて、この太陽系儀は、初心者クラスのものだと判って少しがっかりした。
部品はしっかりしているが、例えば、地球以外の惑星の自転を再現していないし、一番がっかりなのは、ガリレオ衛星や火星、土星の衛星等がただ単に棒で固定されているだけで、それ自体の回転をみることが出来ないこと。
中学校の時に、もっと大型の太陽系儀をみる経験があったが、それは素晴らしく、当然、惑星は公転するし、火星、木星、土星等も自転する上にガリレオ衛星も木星の周回するので、非常に面白かった。
これは、ただ単に、太陽の回りをぐるぐる回るだけである。
土星等の惑星の個体の模型細工が程度がイマイチという点である。こんなものが出来上がって販売されているのかどうか判らないが、精々5~6万円位の商品である。雑誌付きであるが、9万円を越えてくると、ロボットといい勝負で、買わなかった方が良かったかも。
こんなキットがあるのならば、ゼンマイ振り子時計なんかの模型のキット等発売して欲しいと思う。ギアの組み立てなんか、面白いと思う。
トホホ、だが、ここまで来てしまったら、最後まで走るしかないようだ。
太陽系をつくる ジュピターエフェクト ― 2009/08/16 23:31
「太陽系をつくる」の模型の話は、前回の通りだが、今回、特に良かったのがマガジンの内容。
天文や科学史関係のネタで有名な雑誌と言えば、いわずもがな「ニュートン」であるが、あの雑誌は、定期購読していたが、あまりにつまらないので、やめてしまった。
その理由として、専門的な様子でありながら、記事の底が浅く、マニアごのみでなかったことや、科学イラストのクセ(絵のクセなんだからどうしようもない。)が非常に嫌だった点である。動物や天然事象への愛情が絵描きさんに感じられない様な絵だった。影の付け方が特に嫌だった。
「太陽系をつくる」のイラストは素素晴らしい。実写映像とみまがう様な出来映えのものが多い。特に火星の人面石等のイラストは、最高傑作だと思う。
惑星探査機では、その詳細な米ソの観測史、探査機のタイプや航法、メカニズムの詳細なデータも掲載されている。カッシーニ(ホイヘンス)がタイタンに着陸し、実際には、700枚画像を撮影していたのにプログラムミスで350枚しかデータを受信出来なかったことや木星探査機のガリレオは、プルトニウム燃料を積んでいたが、木星への衝突後、分解し、プルトニウム燃料が木星内部の圧力の効果で、熱核爆発が発生し、そのキノコ雲が木星表面に現れて、地上からアマチュアの望遠鏡でも観察出来たこと等、知らなかった事実も多い。
天体観測史では、2000年前のギリシャで、製作された現代技術顔負けに太陽系儀の話。
この機械は、木製の枠に収められていたが、青銅製のギア等、金属部品で構成されていた。海底に沈んでいたギリシャ船から引き上げられた。内部エックス線調査を行ったところ、非常に精密なギア等の機構部品が確認出来、そのエックス線写真が掲載されている。凄いのは、この機械を使うと、月食、日食等の発生日時が予想出来る等、超精密な機械であったこと。
18世紀後半に初めて、大型反射望遠鏡を製作したウイリアム・ハーシェルの話は、有名だが、その後、1840年代に、ウィリアム・パーソンズ(ロス卿)が、口径1.8メートルの当時としては巨大望遠鏡(実際、この口径の望遠鏡は、20世紀前半まで、その後、作られなかった。)を完成し、銀河系外星雲の観測を行ったこと。更に、この望遠鏡が、現代になって復元されており、最新式の装備にリフォームされて使用されていること等、実に興味深く面白い話題が掲載されている。
この外、インド天文学では、特にヒンドゥーの曼荼羅風の天文図、あるいは、私が、つねづね提唱している「木星の引力(潮汐力)が地震の原因となっているという考え方が、実は、「ジュピター・エフェクト」と呼ばれる学説が発表されており、木星を含めた惑星の配列と地震のとの因果関係を説明しようとしている記事がみられた。
実際に、現在、製作している太陽系儀を使用して、ジュピターエフェクトが起こりえる惑星配列の再現法等も解説されている。
ここでは、木星や大型惑星の潮汐力が太陽表面の活動に影響を与え、太陽黒点の増加、あるいは、熱量の低下等で地球の大気・気象に影響を与え、それがプレート移動に伴うエネルギー放射への影響へと転移して、地震が発生すると説明している点である。
例えば、兵庫の大雨、異常気象と静岡大地震との関係、阪神大震災発生の前年の夏にみられた異常な暑さ等も、この様な木星を始めとする大型惑星の活動が影響しているという説。
しかし、この雑誌の解説でも述べている様に、惑星の潮汐力が気象に影響を与えているという考え方には無理がある。むしろ、太陽、木星、月等の潮汐力の複雑なベクトルの組合せが元々弱っていたプレートや地盤に影響を与えて地震発生の引き金になるという考え方の方が妥当な感じがする。
この他、火星観測についてもオポチュニティー等最新の観測データについて専門的に解説されており、火星だけでも3号連続で特集されているので、データの分量も多く、いい加減な天文雑誌よりもずっと詳しく参考になる。イラストも素晴らしい。
写真では、土星関係の写真が息をのむほど、素晴らしいので一見の価値あり。
いずれにしてもディアゴスティーニらしからぬ、手を抜いていないマニアックな蘊蓄に満ちた雑誌記事の内容で楽しめる。
天文や科学史関係のネタで有名な雑誌と言えば、いわずもがな「ニュートン」であるが、あの雑誌は、定期購読していたが、あまりにつまらないので、やめてしまった。
その理由として、専門的な様子でありながら、記事の底が浅く、マニアごのみでなかったことや、科学イラストのクセ(絵のクセなんだからどうしようもない。)が非常に嫌だった点である。動物や天然事象への愛情が絵描きさんに感じられない様な絵だった。影の付け方が特に嫌だった。
「太陽系をつくる」のイラストは素素晴らしい。実写映像とみまがう様な出来映えのものが多い。特に火星の人面石等のイラストは、最高傑作だと思う。
惑星探査機では、その詳細な米ソの観測史、探査機のタイプや航法、メカニズムの詳細なデータも掲載されている。カッシーニ(ホイヘンス)がタイタンに着陸し、実際には、700枚画像を撮影していたのにプログラムミスで350枚しかデータを受信出来なかったことや木星探査機のガリレオは、プルトニウム燃料を積んでいたが、木星への衝突後、分解し、プルトニウム燃料が木星内部の圧力の効果で、熱核爆発が発生し、そのキノコ雲が木星表面に現れて、地上からアマチュアの望遠鏡でも観察出来たこと等、知らなかった事実も多い。
天体観測史では、2000年前のギリシャで、製作された現代技術顔負けに太陽系儀の話。
この機械は、木製の枠に収められていたが、青銅製のギア等、金属部品で構成されていた。海底に沈んでいたギリシャ船から引き上げられた。内部エックス線調査を行ったところ、非常に精密なギア等の機構部品が確認出来、そのエックス線写真が掲載されている。凄いのは、この機械を使うと、月食、日食等の発生日時が予想出来る等、超精密な機械であったこと。
18世紀後半に初めて、大型反射望遠鏡を製作したウイリアム・ハーシェルの話は、有名だが、その後、1840年代に、ウィリアム・パーソンズ(ロス卿)が、口径1.8メートルの当時としては巨大望遠鏡(実際、この口径の望遠鏡は、20世紀前半まで、その後、作られなかった。)を完成し、銀河系外星雲の観測を行ったこと。更に、この望遠鏡が、現代になって復元されており、最新式の装備にリフォームされて使用されていること等、実に興味深く面白い話題が掲載されている。
この外、インド天文学では、特にヒンドゥーの曼荼羅風の天文図、あるいは、私が、つねづね提唱している「木星の引力(潮汐力)が地震の原因となっているという考え方が、実は、「ジュピター・エフェクト」と呼ばれる学説が発表されており、木星を含めた惑星の配列と地震のとの因果関係を説明しようとしている記事がみられた。
実際に、現在、製作している太陽系儀を使用して、ジュピターエフェクトが起こりえる惑星配列の再現法等も解説されている。
ここでは、木星や大型惑星の潮汐力が太陽表面の活動に影響を与え、太陽黒点の増加、あるいは、熱量の低下等で地球の大気・気象に影響を与え、それがプレート移動に伴うエネルギー放射への影響へと転移して、地震が発生すると説明している点である。
例えば、兵庫の大雨、異常気象と静岡大地震との関係、阪神大震災発生の前年の夏にみられた異常な暑さ等も、この様な木星を始めとする大型惑星の活動が影響しているという説。
しかし、この雑誌の解説でも述べている様に、惑星の潮汐力が気象に影響を与えているという考え方には無理がある。むしろ、太陽、木星、月等の潮汐力の複雑なベクトルの組合せが元々弱っていたプレートや地盤に影響を与えて地震発生の引き金になるという考え方の方が妥当な感じがする。
この他、火星観測についてもオポチュニティー等最新の観測データについて専門的に解説されており、火星だけでも3号連続で特集されているので、データの分量も多く、いい加減な天文雑誌よりもずっと詳しく参考になる。イラストも素晴らしい。
写真では、土星関係の写真が息をのむほど、素晴らしいので一見の価値あり。
いずれにしてもディアゴスティーニらしからぬ、手を抜いていないマニアックな蘊蓄に満ちた雑誌記事の内容で楽しめる。







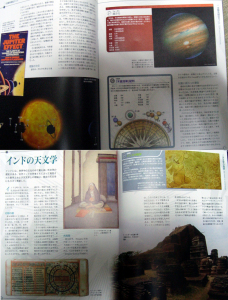
最近のコメント