フルトヴェングラーオリジナルステレオ発見! ― 2010/09/18 09:54
フルトヴェングラーの没年は、1954年なので、既に初期のステレオ録音の実験が行われた時期まで生きていたことになる。
残念ながら、フルトヴェングラーのオリジナルステレオ録音は、残っていないとされてきた。同時代のトスカニーニは、ラストコンサートがステレオ収録、カラヤンは、1944年録音のブルックナーの交響曲第8番の最終楽章が、ドイツ帝国によるステレオ実験によるもので、オリジナルステレオ録音とされている。
フルトヴェングラーの1954年頃の録音を捜してみると、1954年7月26日のザルツブルク音楽祭のライブ録音、ウィーンフィル、ウィーン国利歌劇場合唱団の録音を聴いてみて驚いた。
従来からのライブ録音コンサートは、既に何度かCDで発売されていたが、全て、モノラル録音であった。しかし、この新発見のテープによるCDを聴くと、オケ、歌手の歌唱位置、合唱の左右、舞台上座と下座のノイズ等が異なり、聴取の咳払いも左右に分かれて聞こえる。
ここまで人工でステレオ化を行うことは、難しい。僕もやってみたが、至難の業。
このCDは、プライベート盤である。メトロムジカの音源を元に、オランダで製造されたもので、FV3021-2という番号が振られている。
素晴らしい。あの狩人の合唱もフルトヴェングラーの指揮でステレオで聴けるんだ。
祖父の展覧会を見学して ― 2010/09/18 22:55
今日は、六甲アイランド北口に立地する神戸市立小磯良平美術館で、本日から、開催されている特別展、「古家新とゆかりの画家達」を見学にいった。
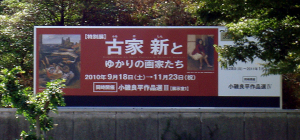

この展覧会、白血病で、死期が近いことを悟った叔母が計画していたが、残念ながら、この展覧会を叔母は目にすることなくこの世を去った。
古家新とは、僕の祖父だが、洒落にならない名前だと思う。「新」と書いて、あらたと昔は読んでいた。
明石市に生まれて、神戸Ⅱ中を卒業後、京都の工芸美術学校を卒業、その後、信濃橋洋画研究所で学んだ。朝日新聞社の美術部に入社後、1928年に欧州に留学した。
当時の関西の洋画界というか、美術や音楽全般に東京に比べて、近代化が遅れていた。当時は、洋画の基礎を習得して、美術作品を創作できるということ自体が先進的であった。
欧州留学時の作品には、佳品も含まれているが、作品のレベル全般に、現在、中学、高校でももっと器用に描ける人もいるだろう。

こんな風に我が国の著名な洋画家全般に習作を描いていた時代である。
それでも、祖父の作品をみると、後年の作風を彷彿とさせる様な作品もいくつか認めること画できる。当時から、祖父は風景画を中心に創作を行っていたが、遠近法とか、構図、描線の精密さよりも、描画対象の質感の組み合わせで、全体の構図を構成する画風であったようだ。
ヴァンスの香水工場の作品(展示番号12、写真はブルターニュの農村風景(展示番号11)は、当時、同じ時に南欧を訪問した仲間の画家の作品と比べると、それぞれの画家の個性が浮き出ている。
この作品は、祖母の存命中は、実家の祖母の部屋にかけられていたので、よく覚えている。この後、祖父が描いた大きな作品があり、これは、今回の展覧会に出品されなかったが、それは、今、母親が毎日を過ごしている居間に掛けられている。
当時、南欧には珍しく、雪が降っていたというヴァンスという街自体が神戸鈴蘭台の様な坂の街であるので、工場を描くこと自体が自ずから立体的な構図を組み合わせることにつながるが、それでも祖父は、遠近法よりも工場や建物の壁や道の色の感じ等、素材の性質にこだわっている。
その後、戦中の時期にある。以前、祖父は戦争画を描かなかったと書いたが、今回の展示でやはり、南洋のを航海する船団の様な絵が描かれており、これが軍艦であると小磯良平美術館では解説されているが、これは間違っている。祖父は、戦争中も港を描くのが好きでよく、スパイと間違われて特高に尾行されたりしていた。
戦中の作品は、戦前の時期と同様にマチュールの精密感を目指しているのだが、やはり、不器用な画家なので成功していない。
そうした祖父の絵に変化が現れるのは、1950年代の後半の時期である。依然として、風景画を描いているが、細部の描画が、戦前の作品に比べて簡素化、象徴化される様になり、印象画風の感じも加わる。
しかし、それよりも興味深いのは、「質的遠近法」(僕の造語である)の発見である。これは、精密な構図による遠近法、あるいは、空気遠近法とも異なる。近くにあるもの、あるいは、中距離にあるもの、あるいは、遠距離にあるもの、それぞれの質感を描き分ける方法である。
質感を重視する為に描線やディテールは犠牲にされる。だから、樹木や地面とかそういった質感の違いさえも画集・写真等ではわかりにくくなる。
これらの作品を以前、私は、印刷された画集でみたことがあるが、技法の退化、あるいは稚拙ささえ感じて、否定的な印象を持った。(展示番号42)

「どうして祖父は、こんなに稚拙な作品を描いたのだろう。」と思った。
ところが実物をみると、そうではないことが理解される。美術館の展示員の人もこの特色を理解していると見えて、額縁のガラスが外されて展示されていた。
しかし、これらの作品は、祖父の大胆な3D実験作品群だったのだ。
鳥取砂丘や、斜面の樹木の作品が1950年代後半の作品であるが、これらの作品は、片眼をつぶってみるとみると、まるで、3D画像の様に、近くにある筈ものが、浮き出てみえる仕掛けになっている。だから、斜面から伸び上がる樹木とか、砂丘の砂の道の起伏等が手に取る様に判る。
代表作としては、冬の長崎の港を描いた作品とか、朝日新聞社のある大阪中之島の風景を描いたものがある。(展示番号43 驟雨)
中之島の風景画(大阪市立美術館蔵)は、夕方か夜の風景、あるいは、夕立前の暗雲で中景が暗くなり、遠景は明るく、近景は、いくつかの柳の樹木がカメラでいえば逆光の位置でとらえられている。
つまり、絵を鑑賞する人は、近景の樹木の裏側の陰をみている感じ。その裏側は、光で輪郭が強調されて、それが、中景の暗さに浮き出して見える仕掛け。
この作品も片眼をつぶってみると、近景の樹木が立体的に浮き出して見える優れた効果を発揮している。
カンバスの近くによってみると、樹木の陰の部分は、絵の具をベタベタに塗り込めて左官屋の壁の様な細工されている。その反対側の光が当たる部分は、筆を比較的細かく使って、輪郭が散乱して強調される様に描かれている。遠景は、アッサリと仕上げており、若干の空気遠近法の技法もみられる。
しかし、この作品は、構図的な遠近法が全く使うことなく、3D表現を行っており、おそらく、祖父の作品の中で、最も技巧的に優れたものだと思う。
1960年代初期まではこの作風が続くが、この技法の欠点である細部の描線の省略は、一般の人には、理解されなかったので、しばらく、方向性が定まらない状態が続く、つまりスランプである。
1960年代に入って、小豆島にアトリエを構えたのも、うなずける。
つまり、「質感遠近法」の限界を打破する為である。この島を一度でも訪問した感受性の鋭い人は気がつくことだが、この島の強烈な光線で、風景から、砂浜の貝殻まで、あらゆるマテリアルが、その存在感を異様な程、強調されて見える。
この島では、もはや、遠近法は必要がない。それぞれの要素が立体的に画面を構成することができるので、それぞれの描画対象の質感に忠実に描くことで、すべてが成し遂げられるのである。
だから、祖父の風景画も小豆島時代に入って、再び筆描のディテールが目立つ様になる。しかし、それは、線が洗練されていないので、雑多な印象を与えることは否めない。
祖父に倣って、小豆島にアトリエを設けた画家たちの作品、榎倉省吾と比較すると、やはり、祖父の絵に似た傾向がみられるが、小磯良平も祖父に倣って小豆島の風景を描く様になるが、冷徹・精妙な描線と構図を中心とした技法で描かれている。最小限の質的表現で、草壁港の風景を描いており、それなりに成功しているが、この島の強烈な光の生命力を描き出してはいない。
祖父の晩年はまさに「光の生命力」の追求である。その為に、一連の「日の出」の絵を描き続けた。日の出の絵の最初期の作品は、描線等の名残もみられるが、晩年に向かうにつれて、チューブから直接カンバスに絵の具を流し込み、それをナイフで盛り上げるという、狂気の様な技法も駆使されており、その光の渦を描き挙げようとしている。絵の具の混色は、極端に少なくなり、ゴッホの絵の様に、原色の点描の組み合わせですべてを表現しようとする。
遺作として展示されていた「最後の日の出」の絵を描いていた祖父の姿は、僕の目に焼き付いている。つまり、この小豆島の日の出の絵は、小豆島で描かれず、兵庫県の実家で描かれたものである。これは、祖父の心の中の小豆島の「光の生命力」の風景を最後の力で紡ぎ出した作品である。
今回の展覧会を参観させてもらって良かったのは、祖父の1950年代後半の作品を分析、再評価する機会が得られたことである。これは、画集等の印刷物では、得られるものではなくて、絵画作品の現物を見て、初めて得られたものである。これは、祖父以外の画家、あるいは、絵画以外の芸術作品でも同様で、やはり、現物を直接目にしないと正確な絵画評論はできないのである。
ブログでは紹介できない画像もあるので、是非、興味ある方は、展覧会に足を運んで欲しい。
ブログでは紹介できない画像もあるので、是非、興味ある方は、展覧会に足を運んで欲しい。
最近のコメント