墓暴きの宗教文化 ― 2009/01/25 10:37
ガリレオの墓を暴いて、遺体からDNAを検出して、晩年の失明の原因を究明するという。
http://www.afpbb.com/article/environment-science-it/science-technology/2560457/3703335
果たして、そんなことをする意味があるのだろうか。キリスト教文化、取り分けローマ・カソリックには、遺体崇拝の文化がある。日本に関連するところでもフランシスコザビエル等の例もある。
熱心なカソリック教信者は、遺体崇拝(聖人・偉人)を行う性癖があるようだ。例えば、あの大作曲家は、アントン・ブルックナーは、1878年に50年前に亡くなったフランツ・シューベルトの改葬・調査(この歌曲王の死因が果たして本当に梅毒であったのか調査する為であったといわれている。)ブルックナーは、修道院に育ち、宮廷オルガニスト等、正に当時にハプスブルクキリスト教文化の中心にいる人物であった。墓が暴かれると、独特の異臭がしたが、それでも作業が続けられていく。やがて、変わり果てたシューベルトの亡骸が現れた。ブルックナーは、ロザリオを手にしながら、その遺体の顔に接吻し、そこらじゅうを撫で回したと言われる。そうして、終日、その作業を食事もせずに見守っていたと言われる。
今回のガリレオの墓暴きというよりも、カソリックキリスト教文化の儀式の様なものと思われる。
日本でも法然上人墓の改葬・火葬を行った記録(1228年)があるが、死後長い年月が経過していたにもかかわらず、そのお顔は、ルルドの泉の少女の様に、さながら生きているようであったという。
恐らく、法然のお弟子さん達もブルックナーと同じ様な振る舞いをしたのだろう。記録には残っていないが。
それは、純然たる信仰そのものの行為であった。
こうした点で、カソリック文化と浄土宗の儀式文化とは類似した点がある様にみられる。法然上人の生前のあり方もイエス・キリストに類似しており、むしろ、釈迦とは異なっていると思う。
釈迦は、生前から組織的な教団運営を考え、そうした教団の中での修行を重視した。死後のことを考えて死後の教団のあり方についても指示を行ったと思う。
法然上人は、念仏の教えが全てであり、教団よりも個々の念仏修行者のあり方が重要である、極楽往生を志す者全てに道が開かれているという考え方で、教団の組織化というよりも、自然と教えを聴きたがる弟子達に囲まれていたのだろう。だから浄土宗の教祖という考えた方はもたれていなかったと思う。その点が親鸞等とは、異なるところだ。
キリストも原罪から全ての人類を救う為に降誕された。受難によって罪をあがなうその人生の途上で多くの弟子達に慕われることなった。
初期の浄土宗は、その点で、「教え」の中心者を失った後に、ようやく組織的な教団が出来上がっていったのだろう。その為には、象徴となるものが必要で、それが御影であり、御廟であった。こうして、シンボルを中心に儀式を行う宗教行事の位置づけが徐々にされていった。
カソリックも法然浄土教と同様に為政者、他宗の弾圧を受けて、その中で、初期教団が位置づけられていた。そうして、キリスト本人が考えようもなかった象徴的性格をこの宗教は持つようになっていった。
私は、幼時からカソリックの教育を受けて育ったが、浄土宗寺院(例えば知恩院)等での儀式を目の前にして、驚く程、類似していると思った。
聖人の遺体崇拝もこうしたところから来ているのだろう。ガリレオも墓が暴かれることによって、21世紀の新しい「宇宙宗教」のシンボル的位置づけがされるに違いない。
ニュートン力学につながる理論物理学の祖であるガリレオが築いた調和的世界は、20世紀の特殊相対性理論、こうした理論を根拠に宇宙現象の観測、解釈が行われ、ガリレオ宇宙の様な神秘的な調和性(異端視されたガリレオも実は、この点では、アリストテレス科学の伝統を受け継いでいる。)が否定された。
調和を否定した世界を訪れたのは、悲惨な戦争であり、20世紀の精神文化は、それ以前の数世紀に比べて殺伐としたものとなった。そうしたものから調和世界を志向しようとしているのが、「ガリレオ信仰・ガリレオ教」なのかも知れない。
しかし、その様な考え方・志向は、既に科学ではなく、宗教に変質してしまっているのである。
写真は、AMAZONに発注したガリレオの指とガリレオの墓
ガリレオの指が、その墓とは別の所に保管されているという。
http://www.afpbb.com/article/environment-science-it/science-technology/2560457/3703335
果たして、そんなことをする意味があるのだろうか。キリスト教文化、取り分けローマ・カソリックには、遺体崇拝の文化がある。日本に関連するところでもフランシスコザビエル等の例もある。
熱心なカソリック教信者は、遺体崇拝(聖人・偉人)を行う性癖があるようだ。例えば、あの大作曲家は、アントン・ブルックナーは、1878年に50年前に亡くなったフランツ・シューベルトの改葬・調査(この歌曲王の死因が果たして本当に梅毒であったのか調査する為であったといわれている。)ブルックナーは、修道院に育ち、宮廷オルガニスト等、正に当時にハプスブルクキリスト教文化の中心にいる人物であった。墓が暴かれると、独特の異臭がしたが、それでも作業が続けられていく。やがて、変わり果てたシューベルトの亡骸が現れた。ブルックナーは、ロザリオを手にしながら、その遺体の顔に接吻し、そこらじゅうを撫で回したと言われる。そうして、終日、その作業を食事もせずに見守っていたと言われる。
今回のガリレオの墓暴きというよりも、カソリックキリスト教文化の儀式の様なものと思われる。
日本でも法然上人墓の改葬・火葬を行った記録(1228年)があるが、死後長い年月が経過していたにもかかわらず、そのお顔は、ルルドの泉の少女の様に、さながら生きているようであったという。
恐らく、法然のお弟子さん達もブルックナーと同じ様な振る舞いをしたのだろう。記録には残っていないが。
それは、純然たる信仰そのものの行為であった。
こうした点で、カソリック文化と浄土宗の儀式文化とは類似した点がある様にみられる。法然上人の生前のあり方もイエス・キリストに類似しており、むしろ、釈迦とは異なっていると思う。
釈迦は、生前から組織的な教団運営を考え、そうした教団の中での修行を重視した。死後のことを考えて死後の教団のあり方についても指示を行ったと思う。
法然上人は、念仏の教えが全てであり、教団よりも個々の念仏修行者のあり方が重要である、極楽往生を志す者全てに道が開かれているという考え方で、教団の組織化というよりも、自然と教えを聴きたがる弟子達に囲まれていたのだろう。だから浄土宗の教祖という考えた方はもたれていなかったと思う。その点が親鸞等とは、異なるところだ。
キリストも原罪から全ての人類を救う為に降誕された。受難によって罪をあがなうその人生の途上で多くの弟子達に慕われることなった。
初期の浄土宗は、その点で、「教え」の中心者を失った後に、ようやく組織的な教団が出来上がっていったのだろう。その為には、象徴となるものが必要で、それが御影であり、御廟であった。こうして、シンボルを中心に儀式を行う宗教行事の位置づけが徐々にされていった。
カソリックも法然浄土教と同様に為政者、他宗の弾圧を受けて、その中で、初期教団が位置づけられていた。そうして、キリスト本人が考えようもなかった象徴的性格をこの宗教は持つようになっていった。
私は、幼時からカソリックの教育を受けて育ったが、浄土宗寺院(例えば知恩院)等での儀式を目の前にして、驚く程、類似していると思った。
聖人の遺体崇拝もこうしたところから来ているのだろう。ガリレオも墓が暴かれることによって、21世紀の新しい「宇宙宗教」のシンボル的位置づけがされるに違いない。
ニュートン力学につながる理論物理学の祖であるガリレオが築いた調和的世界は、20世紀の特殊相対性理論、こうした理論を根拠に宇宙現象の観測、解釈が行われ、ガリレオ宇宙の様な神秘的な調和性(異端視されたガリレオも実は、この点では、アリストテレス科学の伝統を受け継いでいる。)が否定された。
調和を否定した世界を訪れたのは、悲惨な戦争であり、20世紀の精神文化は、それ以前の数世紀に比べて殺伐としたものとなった。そうしたものから調和世界を志向しようとしているのが、「ガリレオ信仰・ガリレオ教」なのかも知れない。
しかし、その様な考え方・志向は、既に科学ではなく、宗教に変質してしまっているのである。
写真は、AMAZONに発注したガリレオの指とガリレオの墓
ガリレオの指が、その墓とは別の所に保管されているという。
エセ討論のプロ先生達 ― 2009/01/25 11:01
今日は、少し遅い目に目が覚めたので、TVをつけると、政治討論ではなくて、オバマ新政権の今後の方向性について学者先生達のご意見を討論形式で聞く番組となっていた。
みんな一流大学の教員や文化人の人達であり、模範生のご意見を聞かせていただく番組だ。
毎週、これまでやっていた政治討論では、恫喝・怒号が飛び出したり、発言者とは別の人が拳を振り上げながら妨害発言したり、うっかりすれば、殴り合いの喧嘩になりかねないので、いい加減なお笑い番組よりもスリリングなので、楽しんでいた。特に自民の国会対策委員長のキレ具合が面白かった。また、共産の代表も感情が出てくると大阪弁で凄みよるから面白い。
こうした面白さは、今回の学者先生達の討論にはみられなかった。行儀良く、スムーズに滞りなく進められていくが、退屈なので、途中で便意を催してからは、番組視聴は中断されてしまった。
政治討論は、討論ではなくて「口喧嘩」である。ただ、殴り合わないだけである。これも殆ど意味はない。一方、学者先生の「ディスカッション」は、「ショー」である。予め筋書きが決められており、方向性も定まっているので、何ら建設的なことはなく時間の無駄である。
デジタル放送なので、それぞれの先生方の主張を文字テロップで表示すれば、それで、事足りる。
こうした、「討論ショー」の傾向は危険だと思う。佛教大学でも様々なシンポジウムが行われるが、「討論・進行・参加者」のプロ先生方演じている見せ物に過ぎない。これは、仕事で学会シンポジウムの取材にいっても同じ様な状況である。
「学びたい」とか、鳴り物入りの宣伝で言ってもガッカリさせられることが多い。(討論なのに予め原稿が準備してある。)
学校教育は、言わば「自由・民主主義」の教育を行うところである。小学校からの学級会の延長が大学・大学院・学会でのシンポジウムであり、その頂点にいるのがアカボス(大学教授)である。
これらの「討論」に共通しているのは、「自由・民主主義」の絵空事を演じる為に行儀良く、他者の意見を聞き、同調していくと言う点である。
文学や芸術等凡そ「自由・民主主義」の路線から離れた学問分野でも、同じ様な「学級会」が運営されている。こうした中で、良い点を貰えるのは、弁舌巧みで協調・融和性があり、理解力・情報組織力(まとめの力)に優れた学生である。
実につまらないと思う。まだ、政治討論会の方がマシだと思う。この様な教育を受けた若者で社会が構成される様になったので、本当の討論が出来ない世の中になってしまった。それが、今の国会や自治体、あるいは、NPO団体の現状である。
「話し合い」では物事が進まない世の中。これは、大変である。話し合われても、本音と建て前の乖離があるので、協同事業は衰退していくのである。
最悪なのは、「裁判員制度」である。「学級会」は、一般民間人が、裁判員に徴用された時に困らない為の教育である。ここでも「エセ討論」に長けた学識経験者や一流企業の人間に支配され、大切な人間の命までもが「建前」・「多数決」で決められてしまうのである。
昨日の歴史発見で岩倉使節団の欧米訪問記がやっていたが、文明国としての偽善者ぶるイギリス等の政治家に比べて、プロイセンの鉄血宰相ビスマルクの発言が一番、現実に即していると思った。
結局、世界・世の中は、話し合いではなくて、「鉄と血」の原理で動いているのだと思う。現代は、「車とガソリン」の原理であるが。
みんな一流大学の教員や文化人の人達であり、模範生のご意見を聞かせていただく番組だ。
毎週、これまでやっていた政治討論では、恫喝・怒号が飛び出したり、発言者とは別の人が拳を振り上げながら妨害発言したり、うっかりすれば、殴り合いの喧嘩になりかねないので、いい加減なお笑い番組よりもスリリングなので、楽しんでいた。特に自民の国会対策委員長のキレ具合が面白かった。また、共産の代表も感情が出てくると大阪弁で凄みよるから面白い。
こうした面白さは、今回の学者先生達の討論にはみられなかった。行儀良く、スムーズに滞りなく進められていくが、退屈なので、途中で便意を催してからは、番組視聴は中断されてしまった。
政治討論は、討論ではなくて「口喧嘩」である。ただ、殴り合わないだけである。これも殆ど意味はない。一方、学者先生の「ディスカッション」は、「ショー」である。予め筋書きが決められており、方向性も定まっているので、何ら建設的なことはなく時間の無駄である。
デジタル放送なので、それぞれの先生方の主張を文字テロップで表示すれば、それで、事足りる。
こうした、「討論ショー」の傾向は危険だと思う。佛教大学でも様々なシンポジウムが行われるが、「討論・進行・参加者」のプロ先生方演じている見せ物に過ぎない。これは、仕事で学会シンポジウムの取材にいっても同じ様な状況である。
「学びたい」とか、鳴り物入りの宣伝で言ってもガッカリさせられることが多い。(討論なのに予め原稿が準備してある。)
学校教育は、言わば「自由・民主主義」の教育を行うところである。小学校からの学級会の延長が大学・大学院・学会でのシンポジウムであり、その頂点にいるのがアカボス(大学教授)である。
これらの「討論」に共通しているのは、「自由・民主主義」の絵空事を演じる為に行儀良く、他者の意見を聞き、同調していくと言う点である。
文学や芸術等凡そ「自由・民主主義」の路線から離れた学問分野でも、同じ様な「学級会」が運営されている。こうした中で、良い点を貰えるのは、弁舌巧みで協調・融和性があり、理解力・情報組織力(まとめの力)に優れた学生である。
実につまらないと思う。まだ、政治討論会の方がマシだと思う。この様な教育を受けた若者で社会が構成される様になったので、本当の討論が出来ない世の中になってしまった。それが、今の国会や自治体、あるいは、NPO団体の現状である。
「話し合い」では物事が進まない世の中。これは、大変である。話し合われても、本音と建て前の乖離があるので、協同事業は衰退していくのである。
最悪なのは、「裁判員制度」である。「学級会」は、一般民間人が、裁判員に徴用された時に困らない為の教育である。ここでも「エセ討論」に長けた学識経験者や一流企業の人間に支配され、大切な人間の命までもが「建前」・「多数決」で決められてしまうのである。
昨日の歴史発見で岩倉使節団の欧米訪問記がやっていたが、文明国としての偽善者ぶるイギリス等の政治家に比べて、プロイセンの鉄血宰相ビスマルクの発言が一番、現実に即していると思った。
結局、世界・世の中は、話し合いではなくて、「鉄と血」の原理で動いているのだと思う。現代は、「車とガソリン」の原理であるが。
LUMIX-G1で撮影した大阪城梅林 ― 2009/01/25 21:17
今日の日曜日は、久しぶりに大阪城梅林に出かけた。まだ、梅の花は咲き出したばかり。
デジカメは、LUMIXのFZ28とデジタル1眼G-1(標準ズームセット)を持参して比較撮影をする。
これは、G1で撮影した画像。G1の撮影で感じたのは、FZ28と同じ画像処理ソフトでもシーンダイヤルのクローズアップモードが使いやすいことである。
また、ピントも最初はオートフォーカスで合いづらかったが、この機械のクセが判ってからは、簡単にピントが合う様になった。梅の花は、クローズアップモード使うべきだと思う。
バリアングル液晶は、期待した程、使いやすくはない。特にレンズを上側に向けて撮影する時、横に開いた液晶から見える画面が上下が逆さになってしまうので、これを天地回転出来る機能をつけて欲しい。
撮影は、AFも速いので非常にスムーズだが、簡単に撮れたと思った割りには、それ程良い写真は撮れなかった。
デジカメは、LUMIXのFZ28とデジタル1眼G-1(標準ズームセット)を持参して比較撮影をする。
これは、G1で撮影した画像。G1の撮影で感じたのは、FZ28と同じ画像処理ソフトでもシーンダイヤルのクローズアップモードが使いやすいことである。
また、ピントも最初はオートフォーカスで合いづらかったが、この機械のクセが判ってからは、簡単にピントが合う様になった。梅の花は、クローズアップモード使うべきだと思う。
バリアングル液晶は、期待した程、使いやすくはない。特にレンズを上側に向けて撮影する時、横に開いた液晶から見える画面が上下が逆さになってしまうので、これを天地回転出来る機能をつけて欲しい。
撮影は、AFも速いので非常にスムーズだが、簡単に撮れたと思った割りには、それ程良い写真は撮れなかった。
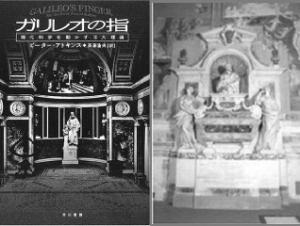






最近のコメント