「Unique」よりもコスト優先の不毛な時代 ― 2009/12/10 21:44
蓮舫議員発言を巡って
民主党蓮舫議員の「№2で何が悪い。」発言は、コンピュータサイエンスの世界で大きな波紋を投げかけている。
「№2で何が悪い。」とハッキリ言葉に出して、これまで言い切る人は、これまでいなかったが、多かれ少なかれ、同じ様な世論は多い筈だ。
しかし、学術研究(理系・人文を含めて)に携わる人達は、この様な考え方、世論には大きな抵抗を持っている人が多い。
つまり、№2とは、№1=「unique」を否定するものであるから。№1とは、世界1でもあるが、それ以上にこれまで世界存在しなかった領域を目指すという点にあるからだ。
例えば、南極探検で、アムンゼンも、スコットも白瀬中尉も、やはり、「№1」=「一番乗り」を目指していた訳で、「僕は、予算がないから№2で良いのだ。」という考え方のチャレンジャーはいない。
学術研究者もチャレンジャーである。
週刊アスキー2009 12/02号の118頁に「仮想報道」の見出しで、歌田明弘氏の論文で、この問題を扱っている。「蓮舫発言に度肝を抜かれた。」、「最先端の科学者たちは、トップを目指して切磋琢磨している。」等「粛正」に反対して科学者が開いた記者会見の内容の概略や、スーパーコンピュータ開発をめぐる主に予算獲得面の動向等も挙げており、公平・妥当な意見を述べているが、科学技術は、やはりトップを目指すと
民主党蓮舫議員の「№2で何が悪い。」発言は、コンピュータサイエンスの世界で大きな波紋を投げかけている。
「№2で何が悪い。」とハッキリ言葉に出して、これまで言い切る人は、これまでいなかったが、多かれ少なかれ、同じ様な世論は多い筈だ。
しかし、学術研究(理系・人文を含めて)に携わる人達は、この様な考え方、世論には大きな抵抗を持っている人が多い。
つまり、№2とは、№1=「unique」を否定するものであるから。№1とは、世界1でもあるが、それ以上にこれまで世界存在しなかった領域を目指すという点にあるからだ。
例えば、南極探検で、アムンゼンも、スコットも白瀬中尉も、やはり、「№1」=「一番乗り」を目指していた訳で、「僕は、予算がないから№2で良いのだ。」という考え方のチャレンジャーはいない。
学術研究者もチャレンジャーである。
週刊アスキー2009 12/02号の118頁に「仮想報道」の見出しで、歌田明弘氏の論文で、この問題を扱っている。「蓮舫発言に度肝を抜かれた。」、「最先端の科学者たちは、トップを目指して切磋琢磨している。」等「粛正」に反対して科学者が開いた記者会見の内容の概略や、スーパーコンピュータ開発をめぐる主に予算獲得面の動向等も挙げており、公平・妥当な意見を述べているが、科学技術は、やはりトップを目指すと
いう強い「意志」がなければ意味をなさなくなる。
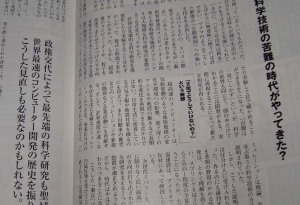
蓮舫議員の指摘に答えた文部科学省の人達は、研究者ではないので、この「肝っ玉」を持っていない為に直ぐに反論することが出来なかったのだろう。
これは、文学研究でも言える。研究論文で、「unique」は、命である。佛教大学の論文指導で共通にみられた「先行研究の調査」とか「先行研究を踏まえて」といった姿勢は、単位取得、あるいは、無難な学位論文(資格試験のようなもの)では、必要かも知れないが、先行研究よりも、やはり、自分の研究テーマや解明した事実、論考、結論に「unique」の要素がなければ、価値はゼロである。
「自分の研究は、未踏峰の頂上に挑んだものである。」と堂々と主張できることが、まず、重要であることは、谷沢永一先生や清水好子先生も言われていたし、佛大の安藤佳香先生もこの点に拘られていたようである。
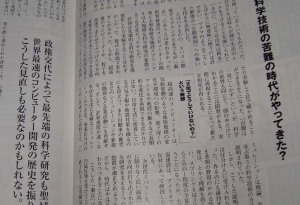
蓮舫議員の指摘に答えた文部科学省の人達は、研究者ではないので、この「肝っ玉」を持っていない為に直ぐに反論することが出来なかったのだろう。
これは、文学研究でも言える。研究論文で、「unique」は、命である。佛教大学の論文指導で共通にみられた「先行研究の調査」とか「先行研究を踏まえて」といった姿勢は、単位取得、あるいは、無難な学位論文(資格試験のようなもの)では、必要かも知れないが、先行研究よりも、やはり、自分の研究テーマや解明した事実、論考、結論に「unique」の要素がなければ、価値はゼロである。
「自分の研究は、未踏峰の頂上に挑んだものである。」と堂々と主張できることが、まず、重要であることは、谷沢永一先生や清水好子先生も言われていたし、佛大の安藤佳香先生もこの点に拘られていたようである。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
「unique」を追求する理由。それは、人間の持つ、無限の可能性の肯定でもある。
私は、古今東西の思想、科学研究史に関する書物を渉猟して来たが、これまでで感じて、このように結論づけた。
それは、「学術研究や技術の発展は、シーケンシャルではない。」ということである。
その点について、例えば、このブログで「太陽系をつくる」で紹介したある発見が示している。
http://fry.asablo.jp/blog/2009/08/16/4520432
それは、『アンティキテラ~古代ギリシャのコンピュータ』(ジョー・マーチャント著、文藝春秋社)に書かれた紀元前1世紀頃にギリシャの海底に沈んだ沈没船から発見された精密な歯車で作られた天体模型である。
複雑なギア数十個で構成された精密機械である。それは、複雑な太陽系と地球の運行をシミュレートし、月食、日食、惑星の移動等を予想するマシンである。
ギアで構成された精密機械が歴史上に登場するのは、11~12世紀の中世ヨーロッパであるが、このマシンに使用されているギアは、17~18世紀の技術水準に達している。
つまり、このマシンは、一般の人間科学史の発達から少なくとも10世紀は進んでいたといえよう。
「unique」を追求する理由。それは、人間の持つ、無限の可能性の肯定でもある。
私は、古今東西の思想、科学研究史に関する書物を渉猟して来たが、これまでで感じて、このように結論づけた。
それは、「学術研究や技術の発展は、シーケンシャルではない。」ということである。
その点について、例えば、このブログで「太陽系をつくる」で紹介したある発見が示している。
http://fry.asablo.jp/blog/2009/08/16/4520432
それは、『アンティキテラ~古代ギリシャのコンピュータ』(ジョー・マーチャント著、文藝春秋社)に書かれた紀元前1世紀頃にギリシャの海底に沈んだ沈没船から発見された精密な歯車で作られた天体模型である。
複雑なギア数十個で構成された精密機械である。それは、複雑な太陽系と地球の運行をシミュレートし、月食、日食、惑星の移動等を予想するマシンである。
ギアで構成された精密機械が歴史上に登場するのは、11~12世紀の中世ヨーロッパであるが、このマシンに使用されているギアは、17~18世紀の技術水準に達している。
つまり、このマシンは、一般の人間科学史の発達から少なくとも10世紀は進んでいたといえよう。

平安時代の遺跡から携帯電話が発掘された様なもの
実際、この本にも、エジプトファラオの墳墓から内燃機関(エンジン)を積んだ車の残骸が発見された様なものと表現されていたが、平安時代の遺跡から携帯電話が発掘された様なものである。
ここで言えるのは、科学技術は、時間の積み重ね(先行研究・技術の積み重ね)の水準を遙かに超えて突然変異・奇跡的に進化することによって、技術水準が上昇していくという点である。
つまり、その時代の№1=「unique」の発明、発見、技術達成が、評価されて、受け継がれることによって、飛躍的に科学技術とは進歩するものなのだ。
しかし、それは、非常に難しく蓮舫議員の「№2で何が悪い。」にみられる様な直接的な(金銭的)価値を求める、それぞれの世の中の凡愚によって多くは埋没され、忘れ去れていく。
そういった人為的な「浸食」を生き残った技術や理論が人類の学術・科学史の発展につながる。つまり、「unique」が時代の淘汰を克服して初めて人類史の成果となる。
民主党の作業仕分けの「仕分け分類」の原理は、「コスト*効果」である。つまり、「この機械はなんの役に立つのか。」という点が重視される。
つまり、「汎用性」が軽視される訳である。
ここで挙げた古代ギリシャのコンピュータは、天体の運行計算が目的に設計されているが、基本メカニズムに差動ギアが接続されており、この差動ギアを差し替えることで様々な計算の目的に使用出来る。
つまり、「汎用性」が軽視される訳である。
ここで挙げた古代ギリシャのコンピュータは、天体の運行計算が目的に設計されているが、基本メカニズムに差動ギアが接続されており、この差動ギアを差し替えることで様々な計算の目的に使用出来る。

「汎用性」を追求しなければ、はるかにコストを抑えて簡便な構造にすることが出来る。例えば、「太陽系をつくる」の模型では、差動ギアが用いられず、水星の回転速度が徐々にギアによって伝達される過程で数分の1、数十分の1、数百分の1まで減速される仕組みで、この機械は、ただ単に簡単な惑星の公転の模倣しかできない。
差動ギアを各惑星系毎に使用すれば、横道面から遙かに傾斜していたり、あるいは、楕円とか小惑星の様に地球の軌道の内部に入り込んでいる天体の運行までシミュレート出来る。
この古代ギリシャの精密メカニズムは、各地に伝わる様々な暦法に合わせることが出来る汎用性をもっていたのである。汎用性とは、「コスト対効果」という考え方に相反するが、科学的応用の第1歩でもある。
スーパーコンピュータも「汎用」計算機である。この点が作業仕訳でも、民主党議員の無理解の原因になったのだと思う。
差動ギアを各惑星系毎に使用すれば、横道面から遙かに傾斜していたり、あるいは、楕円とか小惑星の様に地球の軌道の内部に入り込んでいる天体の運行までシミュレート出来る。
この古代ギリシャの精密メカニズムは、各地に伝わる様々な暦法に合わせることが出来る汎用性をもっていたのである。汎用性とは、「コスト対効果」という考え方に相反するが、科学的応用の第1歩でもある。
スーパーコンピュータも「汎用」計算機である。この点が作業仕訳でも、民主党議員の無理解の原因になったのだと思う。
「時代を超越した無限の可能性」、これが一番、評価されづらいものなのかもしれない。
最近のコメント